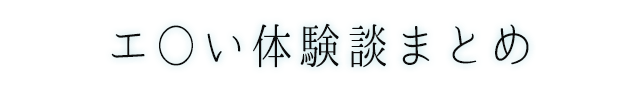白石聡史は一度、目を覚ましたが、今日から夏休みということを思い出し、朝寝坊しようと再び眠りについた。
中学三年の聡史は、朝が苦手だった。
そんな聡史を、母親の鏡子が起こしにやって来た。
「聡史、いくら夏休みでも、けじめはつけなさい」
母親の鏡子は厳しい口調で息子を叱り、部屋のカーテンをさっと開けた。
「うんん、 、お母さん、 、まだ眠いよ」
「朝ご飯は一緒に食べる約束でしょ、早く起きなさい」
聡史は眠い目をこすりながら、部屋から出て行く母親の鏡子のうしろ姿を見つめた。
(お母さんとの約束だけは、破るわけにはいかない)
聡史が一階に降りて行くと、廊下に漂う挽きたてのコーヒーの香りと共に、食堂から姉の声が聞こえてきた。
「やっと今日、内容のある話が聞けそうなの」
聡史の姉、真紀は大手新聞社の社会部の記者だった。
今年、四年制大学を卒業し、この春、なったばかりの新米記者だった。
「なかなか話をしてくれなかったけど、やっと今日、同じクラスの男の子が、いじめのあった場所へ案内してくれるの」
娘の真紀の話を聞きながら、鏡子は優しい目もとに憂いを滲ませた。
「本当に悲しいことだわ、まだ中学生の子供が、いじめを苦にして自らの命を絶ってしまうなんて」
「私もそう思うわ、 、卑怯で、陰湿ないじめは、絶対に許せない」
真紀は、記者となって初めて任された仕事の緊張感よりも、いじめという理不尽な行為への憤りで、熱い血をたぎらせていた。
「お母さん、私、一体どんないじめがあったのかはっきりさせたいの、事実をありのままに報道して、同世代の子供たちや、その親たちにもっといじめについて真剣に考えてもらいたいの」
鏡子と真紀の話しは、先月の初めに、隣町の中学生がいじめによって自殺に追い込まれた事件のことだった。
自殺したのは、学校は違うが聡史と同じ中学三年の少年だった。
「頑張りなさい真紀、 その男の子が話をしてくれる気になったのも、あなたの熱意が通じたのよ」
「きっとそうだと思うわ、私、本当に一生懸命だったの」
真紀は知らなかった。
今日、会うはずの少年は、真紀の真摯な情熱に心を動かされたのではなかった。
その少年は、真紀の体を狙っていた。
恐ろしい罠があるとも知らず、これから真紀は少年のもとへ出かけて行こうとしていた。
「一度、社に顔を出さなくてはいけないから、もう出かけるわ、お母さん」
「そう、しっかり頑張りなさい」
「はい、行ってきます」
母と姉の真剣な雰囲気に気後れした聡史は、食堂へ入るのをためらい入口で立っていた。
出かけようとした真紀が、眠そうに瞼を腫らした弟の聡史に微笑みかけた。
「あら聡史、おはよう」
「あ、おはよう、姉さん」
少し見上げるようにして、聡史は姉に朝の挨拶を返した。
聡史もけっして身長は低くなかったが、真紀のほうがいくぶん高かった。
「もう、まだ寝てるみたいじゃないの、しっかりしなさい、
お父さんが帰ってくるまで、この家の中で男はあなただけなのよ」
「うん、わかってる」
頼りない声で返事をしながら、聡史はうつむいた。
姉に真正面から見つめられると、いつも聡史は自分から顔を伏せた。
それは光り輝く、眩しいものを直視できないことに似ていた。
「じゃ、行ってくるわね」
さっと身をひるがえして玄関に向かう真紀が、爽やかな化粧品の香りを残していった。
聡史は、ゆっくり、深くその香りを吸い込んだ。
(ああ、姉さん)
聡史は思春期を迎えた頃から、真紀を性の対象として見るようになっていた。
互いに少し年齢が離れているせいもあり、女性として美しく成熟しつつある真紀を、
少年の聡史は姉としてではなく、一人の女性として見ていた。
マスターベーションを覚えから、
聡史はペニスをしごく時、姉の真紀を淫らな想像に登場させた。
今では、ただ単に想像の中だけでは抑えられないほどに、姉への想いが募っていた。
「聡史、朝ご飯、早く食べなさい」
鏡子に呼びかけられるまで、
聡史は化粧品の香りを惜しむように、何度も息を吸い込みながら廊下に立っていた。
姉への強い思慕と性欲で、少し赤くなっている顔を母親の鏡子に悟られないように、
聡史は顔を伏せて食卓についくと、いつものように緩慢な動作で食事を始めた。
卵焼きを口の中に入れてから飲み込むまで、聡史はずいぶんと時間を費やした。
そんな息子を母親の鏡子は微笑みながら見守っていた。
「そうだわ聡史、昨日の夜、お父さんから電話があって、
やっぱりあと二ヶ月ほどかかるらしいわ」
聡史の父親は電気メーカーの技術者で、海外へ長期出張していた。
「えっ、二ヶ月も」
「あら聡史、あなた真紀に言われたこと気にしてるの、
いいのよそんなこと、私は、聡史のおっとりした、大らかな性格は大好きなのよ、
ただ時間にルーズなところは直しなさい」
人として生きていくための約束事には厳しいが、他のことには寛容で優しい母だった。
鏡子は、家庭に問題を抱えた女性達を支援する団体、『つばさの会』の主宰者をしていた。中学生の聡史でも、仕事と家庭を両立させるのがどれだけ大変なことかよく分かっていた。一つの組織の責任者として、また家庭の主婦として、毎日とても忙しいはずなのに、
それでも疲れた顔一つ見せない母親の鏡子を、聡史は尊敬していた。
立派な母親を自慢に思い、その息子であることが誇らしかった。
「私もう出かけるけど、今日、塾はお昼からだったわよね」
「うん、それまで予習しようと思うんだ」
「お昼ご飯はチャーハンが冷蔵庫に入ってるから、温めて食べなさい」
母が出かけて行き、広い家に一人になった聡史は、
かねてから密かに思い巡らしていたことを、今日こそ実行しようと思っていた。
聡史は、姉の部屋に忍び込むつもりでいた。
白石真紀は、上司に必要な報告を済ませ、約束した少年と会うため新聞社をあとにした。
半袖の白いシャツに洗いざらしのジーンズ姿の真紀は、
女性にしてはかなり広めの歩幅で、道行く人を追い越し、JRの駅に向かった。
(今日の取材、必ず成功させないと)
自殺した少年の苦しみや悲しみを思うと、真紀は目頭が熱くなった。
あのいじめは、暴力をともなう陰湿なものだったと噂されているが、具体的な内容は、
いまだに不明だった。
警察も傷害事件として調べているようだったが、硬く口を閉ざす生徒達や、
なんとか事件を穏便に終らせようとする学校側の鈍い対応に、捜査は進んでいなかった。
電車に乗った真紀は、取材の要点をまとめたメモ帳を取り出した時、
まとわりつくような男の視線に気がついた。
よくある事だった。
いつものように真紀は、その視線をまったく無視した。
真紀のななめ前に座っているその営業マンは、広げたスポーツ新聞を読むふりをして、
彼女に見とれていた。
(いい女だ)
ラッシュの時間帯は過ぎていたが、車両のシートは埋まり、数人の乗客がつり革につかまっていた。
その中で、きちんと両膝を揃えてシートに座った真紀は手帳にペンを走らせていた。
陰影のはっきりした、整った顔立ちの彼女は、見る者にクールな印象を与えた。
真紀を見つめる営業マンの男根は、なかば勃起していた。
(くそっ、あんな女とセックスできる男が羨ましいぜ)
ショートカットの髪型は、見るからに勝気そうな真紀をことさら気の強い女に見せていた。
その営業マンにとって、真紀のような女の裸を想像し、彼女が心を許した恋人の前で股を広げる姿を想像するのは、ことのほか刺激的だった。
そして同時に、そんな真紀の姿を実際に目にすることのできる幸運な男に嫉妬した。
途中の駅で、
お腹の膨らみが目立ち始めた妊婦が、車内に乗り込んできた。
シートが埋まっている車両の中で、真紀はすっと立ち上がると、その妊婦に席を譲った。
さりげない自然な振る舞いだったが、
そういう行為は意外と周囲の視線を浴びる。
妊娠した女性が感謝で頭を下げると、つかのま柔らかく和んだ表情を真紀は見せた。
周囲の好奇の目を気にもせず、何事もなかったようにドアのそばに立つと、彼女はふたたび手帳を開いた。
真紀がシートから立ち上がったことで、営業マンは彼女の全身を堪能することができた。
真紀の白いシャツをひかえめに盛り上げる胸元や、細くしなやかなウエスト、
そしてジーンズをかたどる引き締ったヒップラインから一直線に伸びる長い足の有様を、
それこそ舐めるように見つめた。
(犯りたい)
全体的に硬さのある体つきからは性的な匂いよりも、人としての清潔感が強く感じられた。
営業マンは、そういう真紀の清潔さに、歪んだ欲望をかりたてられた。
(犯りたい、こういう女を涙が枯れるまで、責めてみたい)
電車から降りた真紀の後姿が窓から小さくなっていくまで、
その営業マンは首をひねって、いつまでも見つめ続けた。
中学校の正門には三人の少年達が待っていた。
「あ、白石さん、おはようございます」
野坂健一の少年らしい、明るい挨拶だった。
「おはよう野坂君、ちょっと待たせたみたいね」
「いえ、僕達が早く来すぎたんです、
それで今日は、友達を二人連れてきました、彼が日下で、こっちが多田です」
ぺこりと頭を下げるその二人は、あどけなさの残る大人しそうな少年だった。
そんな少年達に、真紀は微笑みかけた。
「夏休みなのにわざわざ来てくれて、みんなありがとう」
「白石さんがいろいろ詳しい話を聞きたいんじゃないかと思いまして、
なんとか説得して、二人に来てもらいました」
三人の少年達の中でいちばん背の低い野坂健一は、礼儀正しい言葉使いをした。
しかしその礼儀正しさとは裏腹に健一は、紹介した二人の少年に名刺を渡す真紀へ、
ちらっと、子供とは思えない狡猾そうな目を向けた。
もし真紀が、
健一のずる賢い目の光に気づいていれば、哀しい不幸は避けられたかも知れない。
「それじゃ白石さん、いじめのあった場所にご案内します」
真紀と野坂健一が並んで歩き、その後ろから日下と多田が続いた。
白いシャツから薄っすらと透けて見えるブラジャーのラインや、
硬く丸みをおびたジーンズのヒップラインを、後の少年達がじっと見つめていることを、
真紀は知るはずもなかった。
今日の取材を快く了解してくれた三人の少年たちを、真紀は信じきっていた。
このいじめに関する取材は、真紀にとって隣町の中学校ということもあり、
また誠実さと情熱をかわれて、社会部の記者として初めて一人で任された仕事だった。
これまで毎日のように学校を訪れても、生徒や教師から話を聞くことは出来なかった。
誰もが、その話題を避けていた。
ところが三日前、ある男子生徒が取材に応じてもいいと言ってきた。
その生徒が、野坂健一だった。
その頃、
白石聡史は、姉の部屋に忍び込んでいた。
目的は、真紀の下着だった。
思春期のさなかにある聡史は、
特に最近、日増しに強くなっていく自分の性欲を抑えられなくなっていた。
マスターベーションをする時、思い浮かべるのはいつも姉の真紀だった。
(姉さん、僕の綺麗な姉さん)
実の姉を性の対象とすることに、
強い罪悪感でためらいもした聡史だったが、そのうしろめたさが逆に興奮をよんだ。
姉の顔を思い浮かべ、長身のすらりとした体を想像すると、ペニスが固く勃起した。
だが、そうして射精した後は、きまって激しい後悔と自己嫌悪さいなまれた。
聡史は自分が異常な性癖の持ち主ではないかと悩んだ。
『もうやめよう、こんなのいけないことだ』と、
たとえ想像の中でも、もう二度と姉を汚すようなことはすまいと固く心に誓っても、
次の日にはもう我慢できなくなり、部屋にこもってをマスターベーションを繰り返した。
抑えられない姉への想いに悶々とする聡史も、真紀の着替えや入浴の場面をのぞいたり、
まして直接、真紀の体に触れたりする度胸はまったく無かった。
(ああ、せめて姉さんのパンティーが欲しい)
聡史は、姉の分身となる物が欲しかった。
姉の肌に触れていた物、
しかも、最も秘めた部分に密着していた下着を、聡史は切望した。
姉の下着を見てみたい、触ってみたい、そういう思いに聡史はとり憑かれていった。
以前、
臆病で気弱な聡史がそれこそ決死の思いで脱衣所の籠の中を探ってみたが、
目的の物を手にすることは出来なかった。
白石家の女性たちは、自分の下着はその日のうちに洗うことを習慣としていた。
丁寧に洗われ、乾燥機でもとの状態に戻った下着は、そのままタンスの中に収められた。
それは同居する男たちの目を気にしているという訳ではなく、
常に清潔な身だしなみを心がけている鏡子や真紀の習慣だった。
真紀の下着を見たい、触れたいという欲求を抑えきれなくなった聡史は、
夏休みの初日、その思いを真紀の部屋に忍び込むことによって果たそうとしていた。
真紀と三人の少年たちが歩いていた。
中学校への通りを一つ隔てると、辺りはまったく違う雰囲気になった。
車の走る音も聞こえなくなり、急に静かになった。
そこには、閉鎖され、取り壊しの計画すら頓挫している古い繊維工場があった。
工場の暗い色をした鉄筋の壁はひび割れ、錆びが浮き出てた部分は崩れ落ち、
その廃墟のような建造物の周囲には草木もなく、蝉の鳴き声すら聞えてこない。
中学校からほんの少し歩いただけなのに、辺りには嘘のように人影がなかった。
「あの倉庫なんですけど」
野坂健一が指差す倉庫は、学校の体育館ほどの大きさだった。
繊維産業が好況な時期には、出荷待ちの商品がぎっしり保管されていたはずの倉庫も、
工場本体と同様に、長い年月に耐え切れず鉄筋の壁はボロボロに腐っているようだった。
高い所にある窓ガラスは石でも投げられたのか、ほとんどすべて割れていた。
白石家では部屋のドアに、鍵は付けないことにしていた。
家族間のプライバシーは、お互いの意志で尊重しあうことになっていた。
聡史は、家族の信頼を裏切る自分の行為を恥じてはいたが、
どうしようもなくこみ上げてくる真紀への想いには勝てなかった。
(姉さん、僕の姉さん)
きちんとカーテンが閉めてある真紀の部屋は暗かった。
夏とはいえ午前中の部屋の空気はひんやりとして、微かに化粧品の香りがしていた。
カーテンはそのままにして明かりをつけると、聡史はゆっくりと部屋を見回した。
英語の解らないところを聞きに、何度か来たことのある姉の部屋だった。
本棚には整然と国内外の本が並び、
ベッドの上には紺色をした夏用の掛け布団が、丁寧に折りたたまれていた。
ノートパソコンが置かれた机の上は整理が行き届いており、フローリングの床には
塵一つ落ちていなかった。
聡史はベッドにうつ伏せになり、真紀の柔らかい枕に顔をうずめて息を吸い込んだ。
その枕には、真紀とすれ違うとき、いつも微かに薫る甘い香りが凝縮されていた。
聡史は、『姉さん』とつぶやきながら、
ズボンの中で既に勃起しているペニスをベッドに擦りつけた。
そのまま射精してしまいたい衝動に駆られたが、なんとか我慢すると、
聡史はベットから降りて目的の物を探し始めた。
洋服ダンスの下から二段目の引き出しに、求めているものがあった。
その中の右側には、
たぶん専用のケースなのか、細かく幾つもに仕切られた四角い枠の中に、
丁寧に折りたたまれた真紀のショーツが整然と収められていた。
左側には、ブラジャーが綺麗に並べられていた。
ほとんどの下着の色は白だった。
すべてを手にとって形や感触を確かめたかったが、そんなことをすれば几帳面な姉に、
必ず悟られてしまうと思った聡史は、奥にある白いショーツとブラジャーを抜き取った。
(こんな寂しい所でいじめられていたなんて)
自殺した少年のことを思うと、真紀は胸が痛んだ。
自らの命を絶つ決心をするまでに、どれほど辛い目に遭わされたのか。
それを思うと、真紀は思わず目が潤んでしまった。
古い倉庫の扉に野坂健一が手をかけ、
小柄な体格の割に太い腕で、鉄製の大きなスライド扉を横に引いた。
健一が扉を横に引くだびに錆びたレールが、耳障りなほどの高音でキイキイときしみ、
やっと人が入れる幅に開いた入口から、真紀が先頭になって進んだ。
倉庫の中は、ガラスの割れた高い窓から、幾すじもの光の束が射しこみ、照明など必要ないほどに明るかった。
(あれは、何かしら)
湿ったカビの匂いがする、がらんとした広い空間の一角に、
高い窓から射しこむ光の中で、何か白い物がかすんで見えた。
その白く見える物は、
野坂健一が今朝はやく、あらかじめ用意していた物だった。
そんなことなど知らない真紀は、どんないじめが行なわれていたのか、
その様子を少年たちから聞きながら、そのぼんやり白く見える物に向かって足を進めた。
(これが姉さんの、パンティーとブラジャー)
聡史はそれらを広げ、顔をうめた。
ショーツを裏返し、姉の秘所に密着していた部分には、しつこく鼻を近づけた。
綺麗に洗ってある下着からは、
なんの淫靡な匂いも嗅ぎとることは出来なかったが、それでも聡史は鼻をこすり付けた。
(姉さん、姉さんっ)
聡史はズボンとブリーフを一緒に下げ、勃起しているペニスにショーツを巻きつけた。
聡史は姉のショーツに射精した。
若い少年の性を満足させた聡史は、冷静に枕の位置やベッドのシーツのしわを直して、
ブラジャーは元通りにタンスに戻した。
広い倉庫の片隅で真紀が目にした物は、白いシーツに包まれた敷布団だった。
その敷布団は、むき出しのコンクリートの床に無造作に置かれていた。
しかもその脇には、最新型のビデオカメラが三脚に据えられていた。
(どうして、 、こんな所に)
後ろからついて来ていた少年達の話声が、ぴたっとやんだ。
(まさか)
はっとして振りかえった真紀に、少年達は異様に血走った目を向けていた。
健一が低く笑った。
先ほどまでの礼儀正しさが嘘のように、健一は卑しく笑った。
「あなた達、 、私を、だましたのね」
「今ごろ気づいても遅いよ、白石さんっ」
健一が、真紀の腹部に猛然とタックルした。
素早い健一の動きを避けきれなかった真紀は重心を崩され、敷布団の上に押し倒された。
それが合図のように、日下と多田の二人の少年も、真紀に襲いかかった。
「やめなさいっ」
真紀は少年達に腕を突き出し、長い足を跳ね上げて抵抗した。
抵抗の激しさを物語るように、
真紀の履いたローヒールの靴はあらぬ方に飛び、コンクリートの床に転がった。
少年達は真紀の動きを封じようと、三方から彼女の体にまとわりついたが、
予想を上回る凄まじい真紀の抵抗に、健一は額に汗を滲ませた。
「おい多田、腕だ、腕をつかめ、日下、おまえは足だっ」
いらだつ健一は真紀の腹部や二の腕、太腿のあたりを殴りつけた。
さすがに真紀の顔こそ殴らなかったが、健一の無慈悲な暴力には効きめがあった。
二度目に受けた腹部への強打によって、咳きこむ真紀の抵抗が一瞬弱まった。
すかさず両手を頭の上で交差するようにつかまれ、両足は膝のあたりを抱きこまれた。
「こ、こんな、 、放しなさいっ、 、」
腹部の痛みに息をつまらせながら、それでも真紀は少年達に制止の声を浴びせ、
死にもの狂いで体をよじり、抵抗した。
しかし、多田と日下の二人にがっしりと押さえこまれた真紀の抵抗は虚しいものとなり、
もはや彼女は、少年達から逃れることは出来なかった。
ふうっと息をついた健一は立ち上がると、ビデオカメラのファインダーをのぞきこみ、
仰向けに押さえつけられた真紀の全身をアングルに捉えた。
聡史は、
精液で汚したショーツを手にして、真紀の部屋をあとにした。
自分の手だけによるマスターベーションとは、明らかに違う満足感に聡史は酔っていた。
下着を使った行為が、これほど刺激的なものとは思いもしなかった。
家族の信頼を裏切り、こそ泥のようなまねをして姉の下着を手に入れても、
聡史はまったく罪の意識を感じていなかった。
性欲の虜となり、越えてはならない一線を踏み越えてしまった聡史の心は病み始めていた。
自分の部屋に戻る時、
ふと、母の下着はどんなのだろう、と思った。
この時ばかりは聡史は慌てて、そんな自分の考えを打ち消した。
(なに考えてるんだ僕は、 、お母さんは、僕の尊敬するお母さんだ)
聡史の心の深いところでは、
姉の真紀に対する性欲と同じものが、母親の鏡子にも向けて育っていた。
いまは母親への尊敬の気持ちが勝っているが、何かのきっかけさえあれば、
いつ意識し始めてもおかしくないほどに、強く確かな欲望が生まれていた。
聡史にとっての不幸は、身近にいる女性たちがあまりにも美しすぎることだった。
聡史は知らなかった。
大切な姉が危機に瀕していることを。
そしていづれは、尊敬する母の鏡子までもが、
非道な少年の餌食になってしまうことを知らなかった。
聡史は、机につくと塾の予習を始めた。
ビデオカメラのファインダーをのぞきながら健一が、また卑しく笑った。
「白石さん、しっかり撮ってあげるよ」
多田に腕の関節をねじられ、日下に両足を抱きこまれた真紀は、完全に自由を奪われた。
「楽しませてあげるよ白石さん、僕は結構セックスに自信があるんだ」
「なんですって、 、
私を甘く見ないで、必ず告発して、あなた達に償いをさせるわ」
真紀は柔らかいショートの髪をふり乱し、肩で息をしながら、
健一に鋭い目を向けた。
その鋭い視線をへらへらと笑って受け流した健一は、真紀に近づくと、
彼女の腰にどすっと座り込んだ。
「そんなこと言ってられるのも、今のうちさ」
両手を伸ばして白いシャツをゆるやかに盛り上げている、真紀の乳房を鷲づかみにした。
「っっ、 、」
頭上で、多田に両腕をねじ曲げられているため、
上半身を激しく右左によじって健一の手から逃れようとする真紀の腕の筋肉は引きつり、肩の関節には激痛が走った。
それでも真紀は身をもがいて抵抗を止めなかった。
可能なかぎり、少しでも汚らわしい健一の手から逃れようと懸命だった。
健一は、真紀の白いシャツに深いしわを刻みつけ、乳房に指をくい込ませた。
「白石さん、ペチャパイかと思ってたら、そこそこあるじゃん」
真紀の抵抗を楽しみながら乳房を嬲っていた健一の手が、白いシャツのボタンにかかった。
「おい多田、もっと強く押さえろ」
体をよじる真紀の抵抗がひときわ激しくなり、その真紀の胸元を追うようにして、
健一の指が白いシャツのボタンを外していった。
「へへっ、そんなに暴れて、ボタンが千切れたら帰るとき困るのは、白石さんだよ」
縦に割れていくシャツの胸元から、真紀の素肌と白いブラジャーが現れる。
「、 、馬鹿なことはやめなさいっ」
まだ中学生の少年達が、
このような手段で女性を襲うとは、真紀には信じがたいことだった。
女を罠にかけ、よってたかってその体を貪ろうとする少年達。
その卑劣さに、憎しみがこみ上げてくる。
真紀にとっては、裸にされる恥ずかしさよりも、
少年達への怒りのほうが勝っていた。
「卑怯者っ、あなた達はそれでも男なの、 、こんな、こんなやり方で、 、」
「ふん、素っ裸にしてやる」
健一はシャツをさっと左右に押し開き、
シャツの裾を荒々しくジーンズから引き出した。
ハーフカップの白いブラジャーと、
それに負けない透きとおる白さが眩しい、真紀の素肌がさらけ出された。
すかさず健一は、ブラジャーをぐっと上に押し上げ、
小ぶりでもはっきりと半円を描く真紀の乳房を、両手でつかんだ。
「いつもクールな顔してるくせに、可愛いオッパイしてるじゃない、
白石さんって、何人の男を知ってるのかな、三人、それとも五人?」
健一にしてみれば、真紀のように男を寄せつけないタイプの美人でも、
複数の男性経験は必ずあるはずだというのが、あたりまえの感覚だった。
中学三年で既に和姦、強姦を含めて十人以上の女性と性交の経験がある健一は、
なんだかんだ言っても女はセックスを好み、それを求める生き物だと思っていた。
とても中学生とは思えない余裕を見せて、健一は真紀の乳房をもみこんだ。
しかし健一とは対照的に、真紀を力強く押さえつけている多田と日下は、
首を伸ばし、目を血走らせて彼女の乳房に見入った。
そんな二人に、健一は小ばかにしたような顔を向けたあと、再び真紀に視線を移した。
「白石さんの恋人より、きっと僕のほうがセックスは巧いはずたよ、
へへっ、たっぷり可愛がってあげるからね」
健一が、桜色の乳首に吸いついた。
真紀はぞっとする悪寒で全身に鳥肌を立て、その感触に吐き気を覚えた。
「やめなさい、汚らわしいっ」
白く輝く肌も、硬い乳房も、淡く色づく乳首も、
そのすべてが初めて、男の視線と、男の手と舌の動きを知るものだった。
真紀は処女だった。
もちろん真紀にも付き合っていた男性は何人かいたし、唇を許した男性もいた。
しかし結局、身をゆだねてもいいと思える相手には出会えなかった。
大袈裟に、処女であることを大切にしてきたという訳ではない。
遊びのセックスにも、興味がなかったと言えば嘘になる。
ただ真紀は、自分が心から好きになれる男とセックスをしたいと思っていた。
彼女が二十三歳という年齢で未だに性体験がないのは、そういう相手が、
これまで真紀の前に現れなかった、ただそれだけの理由だった。
「こんなに乳首を硬くしちゃって、白石さんって、意外と敏感なんだ」
健一は硬い弾力のある真紀の乳房をもみたて、音をたてて乳首を吸った。
快楽など微塵も感じていなくとも、
真紀の乳首は刺激に反応して充血した。
硬くしこった乳首をつまみあげた健一が、
敏感な反応をみせる真紀を嘲笑った。
女性の体の繊細な仕組を侮辱する健一に、真紀は新たな怒りをつのらせた。
「いい加減にしなさいっ」
真紀は少年を厳しく叱りつけた。
女性の人格をまったく無視した非道な少年達に、真紀は全身を怒りで震えさせた。
しかし、
声を荒げる真紀を前にしても、健一はへらへらと笑って乳首を嬲り続けた。
「さてと、そろそろ見せてもらおうかなあ、白石さんのオマンコ」
乳房を弄んでいた健一の手が、真紀のジーンズに伸びた。
留めボタンを外され、
ジーンズのファスナーが下ろされるくぐもった音を聞いた時、
真紀は自分の身に起きている非情な現実をあらためて実感した。
(レイプされる)
ジーンズを引き下ろそうと、健一の両手に力がこめられると、
それを防ごうと、真紀は必死になった。
少年達も驚くほどの抵抗だった。
どんなに肩の関節に激痛が走っても、真紀は狂ったように抵抗した。
極限まで身をよじり、腰を右に左にひねって健一の手をふり払おうとした。
しかし、真紀の抵抗のすべては無駄なものだった。
健一によってジーンズは奪いとられ、
露わになった白いショーツと、すらりとした両足が少年達の目にふれた。
真紀が激しく抵抗した動きにつられてなのか、
股間にショーツがより合わさって食い込み、
女の裂目を露骨なまでに示すほど、くっきりと縦じわができていた。
「いつもかっこいい白石さんのスジマンかあ、なんかぞくぞくするなあ」
言いながら健一は、その縦じわの溝を人差し指でなぞった。
真紀は全身を緊張させ、怒りの表情を健一にぶつけた。
「許さないっ、私は、あなた達を絶対に許さない、よく覚えてなさい、この償いは必ずさせるわっ」
「へへっ、好きだなあ、そういう白石さんの気の強いとこ、
はいはい、よく覚えておきます、白石さんがどんな体をしてたかね」
健一はショーツの両端をつかむと、一気に引き下げ、両足から抜き取った。
体毛の薄い体質なのか真紀の陰毛は、
女の亀裂の一端を窺わせるほどに淡く、細かった。
清純とも言えるその有様を目にした健一は、ふゅぅ、と口笛を吹いた。
「まいったなあ、ほんとクールな顔してるわりに、可愛い体してるんだよなあ、
中味がどんなか、楽しみだよ」
健一はそれまで両足を押さえつけていた日下と一緒に、真紀の股間を割り開こうとした。
片方の足を健一が、そしてもう片方を日下がつかみ取り、
二人がかりで真紀の両足を左右に広げた。
どんなに真紀が両足に力を込めても、二人の少年には敵わなかった。
「こんな、 」
「白石さんって、外人みたいだなあ、びらびら、ピンク色してるじゃん」
真紀は、両方の足首が敷布団からはみ出すほどに股間を広げられた。
真紀の両腕を組み敷いている多田は身を乗り出すようにして、
そしてそれぞれ左右の足をつかんでいる健一と日下は、のぞき込むようにして、
真紀の秘められた股間の中心を凝視した。
開かれた両足につられるように、ほころびかけている陰唇に健一が片手を伸ばした。
「これが白石さんのオマンコかあ、
へへっ、乳首を舐められて感じたの? ちょっぴり濡れてるよ」
処女であるが故の鋭敏な体は、
快楽など感じていなくても男を迎え入れる準備を始めていた。
普通の日本人女性とは異なり、
陰唇よりもその内部のほうが濃い紅色に光る真紀の秘肉を健一はいじりまわした。
顔を横にそむけた真紀は、
生まれて初めて、男の前に股間をさらす羞恥に戸惑った。
その羞恥は、真紀に自分が女であることを実感させた。
(こんな、 、)
全身が燃えるような、強烈な恥ずかしさを、真紀はこれまで経験したことがなかった。
男の目の前で両足を広げることがどんなに羞恥を伴うものか、真紀は初めて知らされた。
少年達への怒りを、そして憎しみを、一瞬忘れてしまうほどの恥ずかしさだった。
「あれれっ、白石さん、顔が赤くなってる、
体だけじゃなくて、性格も、けっこう可愛いいんだね」
真紀の片足を押さえ込んだまま、健一は器用にズボンとブリーフを脱いだ。
「淫乱かと思ったら、あんまり濡れてこないね、
もう面倒くさいから、このくらい濡れてればいいでしょ、白石さん、
僕の自慢のチンポで、白石さんの恋人より上手にセックスしてあげるからね」
健一のペニスは見事に勃起しており、その大きさは異様なほどだった。
日下の手助けを得て、健一は挿入の体勢を真紀に強いた。
もう、真紀がどんなに身をもがいても、
上向きに割り広げられる開脚を阻止できなかった。
両足の間に健一の体が割り込みむと、その後ろでは、
立ち上がった日下が、左右に開いた両足首をつかんで持ち上げた。
真紀には、抗いようがなかった。
上半身をしっかり押さえこまれ、そして腰がいくぶん浮き上がるほどに両足を真上に
広げてつかみ上げられてしまうと、その体は力を入れる支点を失ったかのように、真紀が
どんなに腰をひねろうと力を込めても、すべての動きが頼りなく無駄なものになった。
「白石さん、気持ち良くさせてあげるから、仲良くしようね」
健一のペニスの先端が、真紀の女の亀裂をなぞるようにゆっくり上下に這いまわった。
生まれて初めて男性器に秘所を嬲られるおぞましさに、真紀の背すじに悪寒が走った。
口惜しくて哀しい感覚に歯を食いしばって耐える真紀が、
膣口に痛みを伴なう圧力を感じた時、彼女は「いやーっ」と、絶叫した。
その叫び声は、
少年達も、そして彼女自身も驚くほどの大きな声だった。
真紀は、そんな自分の声を不様だと恥じたが、
しかし、叫ばずにはいられなかった。
その叫びは、非道な少年達を最後まで拒もうとする、真紀の魂の叫びだった。
「いやっ、いやーーっ」
「白石さん、もう諦めろよ、
ほら、こうして、ここにはめて、こうやって、ずぶっと」
「、 、うっっ」
膣口に健一の亀頭がめり込んだ瞬間、真紀の体が硬直した。
激痛が背中を突き抜け、真紀は自分の肉が裂ける音を聞いたように錯覚した。
健一のペニスが、じわじわと硬く閉じた膣内を突き破っていくたびに、
真紀の痛みはさらに苛烈に、
肉の裂ける音は真紀の鼓膜へ直接、響いてくるようだった。
「すごい締まりしてるじゃん白石さん、なかなか入らないよ」
真紀の膣内に半ばまでペニスを埋めた健一は、不思議な物を見た。
自分のペニスと、その下の敷布団のシーツが、赤く染まっていた。
それを見たとき健一は、
真紀の生理が始まったのかと思ったが、すぐにその考えを改めた。
真紀の大人びた彫りの深い顔とは、まったくかけ離れて見えるほどの幼さの残る肩の線、
硬い乳房、挿入を拒むようなきつい膣内、真赤な鮮血、そして苦痛にうめく真紀の姿、
そのどれもが健一に、いま自分とセックスしている女が、処女であることを告げていた。
「白石さんって、処女だったの、
おいみんな、笑ってやれよ、この女、いい歳こいて処女だぜ」
苦痛の中でその言葉を聞いた真紀は、精一杯に恨みのこもった目を少年に向けた。
その目を見た健一は、ついに残忍な本性を現した。
真紀の髪をつかみ、極端に傾くほどに真紀の顔を手前に引寄せた。
「どう白石さん、初めての男の味は、 、痛い?、痛いよねえ、
僕のでかいチンポをはめられて、そりゃあ痛いよねえ、
でもねえ、まだまだ、こんなもんじゃないよ」
言葉の終らないうちに、
健一は半ばまで埋めていたペニスを、一気に根元まで突き刺した。
「ううっ、 、」と息を詰らせる真紀の髪をつかんだまま、健一は腰を動かし始めた。
「白石さんみたいな、いい女の初めての男になれて、僕も嬉しいよ、
よく覚えておいてね、これが男の味だよ」
相手の苦痛など一切無視した、己の快楽を満たすための荒々しい健一の腰使いは、
真紀に激痛のみをもたらした。
(こんな男に)
好き勝手に女の体を貪る健一に、真紀は苦痛の中で激しい憤りをぶつけた。
「許さない、 私はあなたを、決して許さない」
健一もそんな真紀へ挑むように、深々とペニスを打ち込んだ。
鋭い突きによって、新たな激痛が真紀の全身を貫いた。
「初めて女にされて、血まで流してるくせに、まだまだ元気がいいね」
健一は腰の動きを早め、真紀の傷を広げていく。
「まったくよく絞まるねえ、やべえ、もう出そうだよ
白石さん、 、たっぷり出してあげるからね」
せわしなく腰を動かす健一が迫りくる快楽に醜く顔をゆがめ、射精の気配を見せた。
真紀も女として、妊娠の危険に怯えたが、黙って目を閉じた。
かりに『避妊を』と訴えたとしても、
健一のような男が、その願いを聞き届けてくれるとはとても思えなかったからだ。
それに、憎い男へ『避妊を』などと、
懇願するような弱気なまねはしたくなかった。
この期に及んで、男に犯される弱い女の姿を、少年達に見せたくなかった。
真紀は激痛に耐えながら必死で無表情を装い、そっと目を閉じた。
上半身にはボタンを外されたシャツが両腕に絡まり、
ずり上げられたブラジャーの下では、
健一の爪が食い込んだ跡のはっきりと残る乳房が、硬く揺れていた。
そんな真紀の姿を、
そして敷布団のシーツの赤い染みまでも、
高精度のレンズをもつビデオカメラが冷酷に記録していった。
大量の精液を浴びた真紀は、嘔吐しそうなほどの汚辱感が去らないうちに、
今度は多田のペニスを膣口に押し付けられた。
それまでの凄まじい抵抗による疲労と、激痛による筋肉の痺れで、
真紀の体にはもう抗う力は残っていなかった。
それでも真紀は、挿入を試みようとする多田へ壮絶なまでの怒りの表情を向けた。
「許さないっ、 、あなたにも、必ずこの償いはさせるわ」
真紀の鬼気迫る怒りに怖気づいたのか、
「ひっ、」と多田は泣きそうな顔をして腰を引いた。
そんな多田の背中を、健一が叩いた。
「なにビビッてんだよ多田、こんないい女、二度と抱けないぞ」
真紀の怒りの表情に怖れをなし、泣きべそをかきながらも、
それでも美しい真紀へのたぎる性欲をおさえ切れずに、多田は彼女を犯した。
健一ほどの大きさではないものの多田のペニスは、真紀にふたたび苦痛をもたらした。
最初は恐々と腰を使っていた多田も、射精が近づくと遮二無二にペニスを突き立てた。
真紀への畏れがいびつな興奮を多田に与えるのか、
「し、白石さんっ」と、彼は情けない悲鳴を上げながら、
それでも彼女の乳房をねじ切らんばかりに乱暴にもみたて、射精して果てた。
多田と同じように日下も、真紀の恐ろしい怒りの表情から目をそらしたまま、
叩きつけるような勢いでペニスの出し入れを繰り返した。
日下が射精する頃には、
真紀の体は破瓜の痛みが麻痺するほどに疲労していた。
多田と日下の二人は、呆けたように精液の流れ出る真紀の股間をのぞきこみ、
女性器を指先で嬲った。
健一は、しつこいほどに乳房をもみ、乳首を弄ぶように悪戯した。
真紀には、それらをはね返す体力は残っていなかった。
しかし真紀の心は、非道な少年達への怒りで燃えていた。
きっ、と少年達を睨みつけ、殺気を感じさせる低い声で言い放った。
「もう気が済んだでしょう、 、出て行きなさいっ」
その声に驚き、首をすくめて、慌てて真紀の股間から手を引いた多田と日下の二人とは逆に、健一だけは真紀に臆せず、残忍な顔を彼女にむけた。
健一の言葉使いまでも、一変した。
「なんだとお、気にいらねえな、その目、
処女だったくせによお、俺たちに犯られて、もっと哀しそうな顔をしろよ」
健一は指先に力を入れ、弄んでいた乳首をひねりつぶした。
「出て行けだとお、馬鹿やろう、まだまだ終わりじゃねえんだぞ」
健一の合図で、少年達は真紀の上半身に残っていた衣服をすべて剥ぎ取った。
シャツとブラジャーを奪われると、真紀は強引にうつ伏せにされた。
「おい日下、ロープと、それから例の物だせよ」
ビデオカメラの三脚の下に置いてあるスポーツバッグの中を日下が探るあいだに、
健一は真紀の両腕を背中でねじり合わせた。
「へっへへ、
犯るときは暴れるのを無理やり押さえつけるのがいいんだけどなあ、
これからはちょっと手が邪魔なんだよ」
(この子達はいったい何を)
背中で交差された両腕にロープが絡みつき、真紀の不安を煽るように強く縛められた。
うつ伏せにされると真紀のウエストの細さと、
ヒップラインの硬い丸みがことさら鮮やかに浮き彫りになる。
「次の、お楽しみは」
健一は、真紀の二つに割れて盛り上がる臀部の片方をつかむと、
その肉を押しやるように谷間を広げて、彼女の肛門をむき出しにした。
健一の視線を拒むようにすぼまる真紀の肛門は、
色素の沈着が少なく、放射状の細かなシワさえも桃色をなしていた。
「ふんっ、尻の穴までピンク色なんて、めずらしい女だぜ」
思わぬところに興味を示す健一に、真紀は身を硬くした。
少年達の意図が、真紀にはまったく分からなかった。
羞恥心の強い真紀は、怒りで全身を震わせなからも、
自分ですら見たことのない排泄器官に少年達の視線を感じ、また顔を赤く染めた。
「真紀、たっぷりいじめてやるぜ」
「何をするのっ、 、あっ、 、痛ぅっ」
肛門に、刺すような痛みを真紀は感じた。
多田に両肩を押さえつけられ、日下に両足をつかまれ、そしてうつ伏せにされて両腕を
縛められていては、その痛みから逃れようと最後の力をふりしぼって身をもがいても、
真紀の抗いはなにほどの効果もなかった。
感覚的に、なにか細い物が、排泄器官に差し込まれたことが分かるものの、
それがもたらす痛みに耐えかねた真紀は、それを押し戻そうと無意識に肛門をすぼめた。
その時、腸内に液体のしぶきが、強い圧力をともなって一気に流れ込んできた。
「んっっ、 、 、な、何をしたのっ」
窮屈な姿勢でも、なんとか後ろの健一にふり返ろうともがいた時、
ふたたび肛門に痛みが走り、またしても腸内にしぶきを感じた。
「うっっ」
直腸の粘膜をちりちりと刺激する液体に、真紀は鳥肌を立てた。
(この子達は、 、)
経験のない真紀にも、健一が何をしたのか分った。
それを裏付けるように、横向きにされている真紀の顔の正面に、
健一が放り投げた二つの小さな、ピンク色をしたプラスチック容器が転がった。
いびつに一部分が潰された容器は、まぎれもなくイチヂク浣腸だった。
健康な真紀は、これまで使ったことは無かったが、
一つの常識として知ってるものが、目の前に転がっていた。
「もう一個、あるんだぜ」
健一はひときわ深く容器の先端を真紀の肛門に突き刺し、
薬液の入っている丸く膨らんだ部分を、おもいっきり力を込めて押し潰した。
その薬液のしぶきは、一粒一粒が小さな針のように、真紀の腸内を襲った。
たとえようの無い悪寒と、初めて知覚する腸内の焼けつくような刺激を、
真紀は冷たい汗をかきながら、必死に耐えた。
真紀は、背中で両腕を縛められたまま、
無理やりブリキのバケツを跨がされていた。
「はっはは、すげえ格好じゃない、白石さん」
ビデオカメラを手にした健一が真紀を嘲った。
汗で光る額に前髪をまとわりつかせ、真紀は刺しこむ便意に耐えていた。
真紀も新聞記者のはしくれである。
新聞の紙面に載ることの無い、悲惨なレイプ事件を数多く知っていた。
凌辱された女性達が、どれだけ心と身体に傷を残したか見聞きする機会もあった。
そんな時、
真紀は、冷酷で変質的な方法で女性を辱める男達を心底憎んだ。
真紀は女性を襲う男達を、決して許してはならない思ってきた。
それだけに、自分自身が凌辱の対象にされた今、
少年達に向けられる真紀の憤りは凄まじいものだった。
しかし、
既に限界に達している便意と苛烈な腹痛で、血液の流れは凍りつき、
真紀の全身は蒼白となって、脇腹や太腿の筋肉が痙攣していた。
「へっ、もう我慢できないんだろ、
こういう時は『見ないで』とか『お願い許して』とか言うもんだぜ、
ぶるぶる震えてるくせに、澄ました顔するなよ」
必死に便意を耐える真紀は身体を引きつらせていたが、
その表情はきりっと冴え、
目を閉じて、少し上に向けたその顔はいつにも増して美しかった。
真紀は、少年達に許しを乞うことなど、けっしてしまいと誓っていた。
強制的な排便はもはや避けられないとしても、
不様にうろたえる素顔を見せたくなかった。
それは真紀の、女性としての最期の誇りだった。
「そんなに見たければ、 、見るがいいわ」
場違いなほど冷静な声で、真紀が言った。
その直後、倉庫内に破裂音が響いた。
ブリキのバケツを跨がされた真紀は、
その中に薬液で溶かされた軟便を飛び散らせていった。
真紀の耳に、自らが発した破裂音が残酷にこだまする。
そして立ちのぼる匂いまでも知覚してしまった真紀は、上体をそらし、天を仰いだ。
少年達のはしゃぐ声と食い入る視線のなかで、
真紀の肛門は、固形物をひねり出した。
真紀は、顔を震える肩にそっとうずめた。
それは今日、少年達に初めて見せた、女らしい仕草だった。
覚悟はしていても、排泄を見世物にされることが、
女にどれほどの辛さを強いるか、真紀は苛烈なまでに思い知らされた。
「いつもクールな顔してるくせに、ウンチは臭いよ、白石さん」
三人の少年達とビデオカメラの前で、真紀は排泄を終えた。
その真紀を敷布団の上に引きずり倒した少年達は、
うつ伏せにした千穂の臀部を高く持ち上げた。
後手に縛られたままの真紀には、横向きになった右の頬にすべての体重がかかり、
背中がいびつに曲るほど肛門を真上にさらされた。
「こんなに汚して、今拭いてあげるよ、白石さん」
おどけた口調の健一は真紀をからかいながら、ティッシュで肛門を拭った。
自分ですべき最も人間的な行為を、健一によってなされた真紀は、
目も眩むような羞恥で全身を赤く染めた。
目の前に、
健一が無造作に放り投げたティッシュが落ちてきた。
排泄のあとが真っ白なティッシュにこびり付いていた。
(恥ずか、しい、 、)
みじめな姿のまま、こみ上げてくる恥ずかしさに頬を真っ赤に染めた。
「あれえ、白石さん、顔が真赤になってるよ、
肛門を拭かれるのって、そんなに恥ずかしいの、
へっへへ、可愛いぜ、真紀さんよお」
健一は、多重人格者のように、顔つきや言葉を変え、真紀を嘲った。
そして、肛門のしわをなぞるように、しつこくティッシュを使った。
一人の女性として自立した真紀ゆえに、
排泄後の処置を他人の手で為されることに強い羞恥を覚えた。
(はっ、 なに、 、)
真紀は、排泄器官に冷たい液体を感じた。
健一は真紀の肛門にローションを塗りこみ、人差し指をねじ込んだ。
「くっっ」
吐き気をともなう衝撃で、真紀の腰がよじれた。
「白石さんの処女は、ぜんぶ僕がもらうからね」
肛門の絞まり具合を指先で確かめた健一は、
勃起したペニスを真紀の肛門に押しつけた。
真紀には、ことの現実がにわかには信じられなかった。
(この子は、 、)
「そんな、 、狂ってるわ」
身動きを封じられた真紀を、背後から押し潰すように健一がのしかかった。
「ここですると、やみつきになるらしいよ」
「やめ、っぐ、 、 、」
肛門に健一の亀頭がめり込んだ時、真紀の呼吸が止まった。
歯を食いしばって耐える真紀の細いウエストを健一は鷲づかみ、
一気にペニスの根元まで、肛門を深く貫いた。
衝撃の反動によって、真紀が息を吸い込んだ音は、かすれた喘ぎ声に似ていた。
「白石さんの肛門を犯せるなんて、最高だよ」
真紀のもがき苦しむさまは、健一を楽しませた。
楽しみながら健一は、ペニスを肛門へ出し入れした。
ローションによって裂傷こそしなかったものの、
排泄器官を襲う苦痛と衝撃に真紀は、声すら上げられず、
途切れがちな呼吸を繰り返した。
常識外の部分で交わっていることで、次第に興奮の度合いを高めた健一の目は、
狂気を帯びてきた。
「はあはあ、白石さんっ、」
健一は執拗に、激しく腰を使った。
真紀に獣のようにのしかかり、鷲づかんだウエストに爪を食い込ませ、
思いのままに、真紀の肛門を蹂躙した。
健一は、真紀の肛門に射精した。
しかし、それでも満足できないのか健一は、
うつ伏せに横たわる真紀の髪をつかみ、顔を上げさせるとその前にあぐらを組んだ。
肛虐の苦痛とショックで、
意識が朦朧としかけていた真紀にも、健一の意図が分かった。
少年のペニスを真紀はかすれた声で拒絶した。
「そんなこと、絶対にいやっ、」
髪をふり乱して、真紀は拒んだ。
健一は、日下と多田に命じて真紀の頭を押さえつけさせた。
少年とはいえ、男三人がよってたかって、
一人の女性にフェラチオを強いようとする有り様は、あまりに惨いものだった。
一人は真紀の耳を千切れるほどにつかみ、また一人は髪をつかんだ。
そしてもう一人は、真紀の口をこじ開けようと顎をつかんだ。
真紀の人格を無視した、残忍な行為だった。
射精したばかりにもかかわらず、
健一は硬く勃起したペニスを、強引にこじ開けた真紀の口内へ押しこんだ。
「っむ、 、」
潤いのある真紀の唇が、健一のペニスによってその形を変えられていった。
無理やりこじ開けられた顎のラインと、それよって強調された整った鼻筋が、
少年にフェラチオを強いられる真紀を、残酷なまでに美しく見せていた。
健一は、自分のペニスを口に含ませた真紀の横顔をじっと見ながら、
つかんだ真紀の頭を上下に揺さぶった。
真紀はうつ伏せのまま、哀しい奉仕を強いられた。
(憎い、 、この男が憎い)
何もかも、暴力と腕力によって強いられた行為だった。
(憎い、 、)
瞬間、真紀は本気で、ペニスを噛み切ろうとした。
口内を蹂躙し、喉を突き上げる健一のペニスを、本気で噛み切ろうとした。
しかし、できなかった。
非道な男たちを前にすれば、自分も弱き女であることを、真紀は悟った。
真紀は、全身からすべての力を抜いた。
「かぁー、たまらないや」
健一は、好き放題に真紀の口内を犯した。
多田も興奮し、真紀の胸をもんだ。
乳房をもみながら滑らかな背中に舌を這わせた。
日下は、真紀の腰を持ち上げ、背後から犯そうとのしかかっていく。
「おい日下、尻の穴は俺のもんだからな」
分っていると目で頷く日下は、真紀の膣口にペニスを突きたてた。
それからの真紀は、少年達におもちゃにされた。
健一には、喉の奥深くをつかれ、口内に射精された。
日下と多田は、交互に真紀の唇と膣を犯した。
真紀はふたたび出血した。
すでに両腕を縛めていたロープは解かれていた。
少年達は真紀の身体を弄んだ。
多田は小ぶりで硬い乳房に執着した。
日下はすらりと引締まった太腿から足首までを繰り返し舐めた。
その様子を、健一がビデオカメラで記録していった。
時刻は午後の三時をすぎていた。
ようやく少年達は満足したのか、荒い息をしながら真紀を見下ろした。
仰向けに横たわる真紀の唇の端から、
広げられた股間から、少年達の精液が流れていた。
敷布団からはみ出していた片足を静かに引き寄せた真紀は、
乳房をかばうように両腕を胸にまわすと、少年達に背を向けた。
「もう、出て行って」
真紀の声が、哀しく倉庫に響いた。
「へっ、あれだけ犯らて、まだそんな偉そうに、
おい、分ってると思うけど、こっちにはビデオもあるし、
警察になんか言うなよ、
それに、あの馬鹿が自殺したこと、
もう調べるなよ、いじめた俺達にとっては、えらい迷惑だからな」
少年達が引き揚げていった後、
静かな倉庫で一人きりの真紀は、身を横たえたままじっとしていた。
天井を見つめる真紀の心にあるのは、無念の思いだった。
少年達の本性を見抜けなかった愚かさ、
暴力によってレイプされ、あらゆる辱しめを受けた事実、
そして自分の体が、少年達を悦ばせた口惜しさ、
何もかもが、無念だった。
緩慢な動作で身を起こした真紀は、
突然むせかえる嘔吐感に咳きこみ、胃液を吐いた。
その胃液には、少年達の精液も含まれていた。
真紀は、自分のバッグから懐紙を取り出し、顔をそらせて股間をぬぐった。
ぬぐってもぬぐっても、新たな精液があふれてきた。
散乱している衣服は所々ほこりで汚れ、
白いブラジャーも白いショーツも同様だった。
真紀が、ゆっくりと衣服を身につけるその姿を、
健一が鉄の扉の陰から盗み見ていた。
多田と日下を先に帰した健一は、
なんとしても犯された後の、一人でいる真紀の姿を見たかった。
犯され、恥をかかされた女が、どんな顔をしているのか、見てみたかった。
引きずるような足取りで扉に向かう真紀から隠れるように、
健一は向かいの木陰に身を潜めた。
倉庫から出ようとした時、
真紀は股間にじっとりとした生暖かいものが広がるのを感じた。
膣内に残っていた少年達の精液が流れ出たものだった。
真紀は扉に寄りかかった。
その蒼ざめた頬に、ひとすじの涙が流れた。
少年達の前では、けっして見せることのなかった真紀の涙だった。
無念の思いに、真紀は鉄の扉に爪を立てた。
その様子を、
木陰から健一が残忍な笑みをうかべてじっと見ていた
その日、
白石聡史は塾が終ったあと友人の家に寄り、帰ってきたのは七時をすぎていた。
すでに帰宅していた母親の鏡子が夕食の準備をしていた。
清潔なキッチンの中で、
丁寧でも、手際のいい動きを見せる鏡子が聡史にふり向いた。
「あら聡史、お帰りなさい」
いつもと変わらない優しい母の声だった。
(どうして僕のお母さんは、いつもあんなに素敵でいられるんだろう)
中学生の聡史にも自分の母親の仕事が、
神経をすり減らす厳しい内容であることはよく分っていた。
鏡子が主宰する『つばさの会』は今ではボランティアの枠をこえ、
一種の公的機関として認知されるほど、重要な存在になっていた。
家庭内暴力、夫からの暴力、 、
さまざまな問題を抱える女性たちにとって、欠くことのできない組織だった。
そこでの鏡子は多忙を極め、
また責任者として、けっして間違いの許されない決断を迫られた。
聡史にもそのことが分かっているだけに、
家族の前で疲れた顔や、ストレスの欠片さえみせない母親を聡史は尊敬した。
姉と母、聡史にとっては二人とも慕い憧れる同じ肉親でも、
姉の真紀に向けられる歪んだ欲望と、
母親の鏡子への畏敬の気持は、その時の聡史の中では矛盾するものではなかった。
「ねえお母さん、姉さんは今日も遅いの」
午前中、はじめて姉の部屋に忍び込み、下着を盗んで自慰にふけった聡史は、
いまだに続く興奮と罪悪感とで姉のことが気になった。
「珍しいこともあるのね、あの真紀が頭が痛いといって寝てるのよ、
会社も早引けしたらしいわ、悪くならなければいいのだけれど」
聡史はどきっとした。
自分がした卑猥な裏切り行為が、
姉に祟ったのではないかと迷信じみた思いにかられた。
しかし以前、姉が風邪をひいたときに見た潤んだ瞳を思い出し、
病に蒼ざめる美しい姉の顔を想像すると、聡史は股間が熱くなった。
真紀は真っ暗な部屋の中でベッドに横たわり、
身じろぎもせずに闇を見つめていた。
股間に残る痛みと異物感が、真紀を苦しめた。
この自分の身体で快楽を貪った少年達に憎しみがつのった。
まばたきもしない真紀の瞳から、静かに涙が流れた。
一階の食堂で夕食をとる鏡子と聡史は、そんな真紀の姿を知るはずもなかった。
真紀はその翌日から出社した。
朝食の時、頭痛は治まったと母と弟に笑顔を見せた。
ともすれば暗く沈みこんでしまう自分自身を叱咤し、気力を奮い起こした。
あの少年達に負けてはいけない、という思いが真紀を支えた。
だが必死に抵抗したことによる全身の筋肉と関節の痛みが、
そしてなおも残る股間の痛みが、昨日の屈辱的な記憶を鮮明に蘇えらせた。
それから数日、真紀は何度も専門の弁護士や、警察を訪ねようとした。
一度など弁護士事務所のドアの前まで行ったこともあった。
しかし、どうしてもドアを開けることができなかった。
真紀は自分の女としての弱さを思い知った。
少年達を罰したい気持は強かったが、
法廷で自らが受けた辱めのすべてを、さらす決断が真紀にはできなかった。
あのビデオの映像だけは、誰にも見られたくなかった。
誇り高い真紀は、そんなことは絶対に避けたかった。
そしてもう一つ、
日ごとに真紀を苦しめていくのは妊娠への不安だった。
若い少年達の精液をあれだけ何度も身体の奥深くに注ぎこまれては、
妊娠は避けられないと思った。
最も頼りになる母に打ち明けたかったが、
そうすればきっと母も自分のことのように哀しみ、苦しむに違いなかった。
もしも次の予定日に生理がなかったら、そのときは、 、
(中絶、 、)
真紀は女として哀しい言葉を思い浮かべた。
鏡子はここ一週間、
娘の真紀の様子がいつもと違うことを、ずっと気にしていた。
親の眼から見ても娘の真紀は美しく映ったが、
何か悩みを抱えているように思えてならなかった。
「真紀、今日は久しぶりに駅まで一緒に行きましょ」
いつも自分より早く出かける娘に合わせて、鏡子は支度を済ませた。
「お母さん達もう出かけるけど、聡史も今日は早いんでしょ」
「うん、もうちょっとして行くよ」
息子に戸締りを頼み、鏡子は娘と一緒に家を出た。
二人は眩しい朝日の中を、ゆっくりとした足取りで並んで歩いた。
駅まで十分足らずの緑の多い住宅街を、母娘は世間話をしながら歩いた。
「真紀、今日は晩ご飯食べた後、二人でワインでも飲まない」
駅が見えたころ、鏡子は娘に優しく言葉をかけた。
真紀は、はっとした。
(お母さんは私が悩んでいることを知ってる)
大変な仕事を持ちながらいつも家族のことを気にかけ、
敏感に自分の苦しい胸のうちを感じとってくれる優しい母の言葉に、
真紀は目頭を熱くした。
あふれそうになる涙を必死にこらえ、真紀は笑顔を作った。
「私とお母さんだったら、ワイン一本じゃあ足りないわ」
「あら本当ね、分かったわ、美味しいワインを二本、買って帰るわね」
そんな母娘の様子を、
駅の柱の陰から、一人の少年がじっと見ていた。
野坂健一だった。
健一は、美しい二人を見て股間を充血させていた。
特に健一は、真紀の隣りにいる女性に注目した。
(あの女は母親か、へへっ、いい女じゃん)
白い半袖のブラウスと、膝が隠れるほどのグレーのセミタイトのスカート、
その地味な服装が、鏡子本人の魅力をことさら浮きあがらせていた。
しだいに距離が狭まり、ほとんど目の前で鏡子を見た健一は、唾を呑みこんだ。
(いい女だ)
娘に顔を向ける鏡子の首すじの細さは、真紀よりも際立っていた。
(オバンのくせして、いい身体してしてるじゃねえか)
いかにも仕事を持つ女性らしく、きっちりとセットされた艶ある黒髪と、
優しい目もとを彩るかすかな小じわが、成熟した大人の女性を思わせた。
(犯りてえ)
すっと立っているだけでにじみ出てくる品の良さと、人としての威厳は、
年若い健一を威圧したが、だからこそ健一は、そんな女を泣かせてみたかった。
(あの口でフェラチオさせてえ)
薄くひいた口紅が上品に映える鏡子の唇に、健一は欲情した。
これまで街で見かけた美しい主婦のあとをつけ犯したことのある健一も、
真紀の母親ほど性欲を刺激された大人の女を見たことがなかった。
(あの女、くそっ、犯りてえ)
確かに四十歳は超えて見えた、しかしそれでも瑞々しいほどの美しさだった。
鏡子の重ねた年齢が、そして人生の歴史が、
彼女を美しい大人の女にしていた。
方向が違うのか鏡子はすぐ前の改札に向かい、
真紀は反対側の改札口へと地下道に入っていった。
健一はいっとき鏡子の後姿を堪能したあと、
真紀を追って地下道への階段を駆け降りた。
ちょうど真紀が階段を昇り始めたときに健一は追いつき、
そのすぐ後ろにぴったりとついた。
社会部の記者として行動しやすいように、
真紀はいつも通り、ジーンズに白い半袖のサマーセーターという身軽な服装だった。
健一は、硬さのある真紀のヒップラインを見つめた。
(俺がこいつを女にしてやったんだ)
一週間前、
真紀の処女を奪い、肛門まで犯した健一は、
その優越感からか余裕をもって真紀の臀部の切れこみを眺めた。
真紀が昇りの階段に足をかける度に、ジーンズの裾からのぞく足首が鋭く引き締まり、
それはペニスで味わった真紀の膣の収縮と、肛門のすぼまりの強さを健一に連想させた。
(こいつもいい女だ)
「白石さん」
階段を昇りきったところで、健一は後ろから声をかけた。
出勤前の足早な人の流れのなかで、真紀は立ち止まった。
しかし、ふり向く素振りも見せず、すぐに歩き始めた。
「待ってよ、白石さん」
意外な真紀の反応に健一はいくぶん慌てた。
背の低い健一が、
すらりと背筋を伸ばして歩く真紀にまとわり付くようにしてあとを追った。
「止まれよ、あのビデオ、
親父さんやお袋さんの知り合いに観せてもいいのかよ」
(なんて卑怯な)
真紀が恐れていたことが起きた。
ビデオの存在を脅しの材料にし、
しかも家族を巻きこもうとする健一にあらたな憎しみがつのった。
(私が拒めば、この子は言葉通り実行するにちがいない)
真紀は父を、そして優しい母を哀しませたくなかった。
改札口に向かう人の流れをふり切るように、
真紀はわきへそれ、大理石の柱の前で止まった。
「今日で終わりにするよ、しつこく付きまとうほど僕は馬鹿じゃないよ」
背を向けたままの真紀に、健一はさらに言葉をつなぐ。
「嘘じゃないよ、これで最期だよ、
それに多田と日下の二人は心配ないよ、
僕がいないと何もできない奴らだし、
だから、今日は白石さんの家で、ねっ、ねっ」
巧みに子供らしい言葉使いと、乱暴な物言いを使い分ける狡猾な健一に、
真紀は唾を吐きかけてやりたかった。
憎んでも余りある男だった。
その男が、また性欲をむき出しにしてきた。
きっとまた、屈辱的なことを強いられるのは真紀にも分かっていた。
それでも、真紀には辛い決心をするしか、道はなかった。
さっとふり向いた真紀の表情は、
冷酷な健一でさえびくっとするほど冷たく凍りついていた。
「これっきりにすると約束しなさい」
相手の心に沁みこませるような強い響きに、健一は何度も頷いた。
健一を無視するように真紀は視線を遠くにあてると、
ふたたび地下道へと向かった。
まっすぐ前を見つめて歩く真紀の速さに健一はついて行けず、
ときおり小走りで広がる間隔を縮めた。
聡史は一週間前、
姉の真紀の部屋に忍び込んでから勉強に集中できなくなっていた。
姉が素肌に身につけていた下着の感触を知って以来、
聡史が姉に向ける欲望はさらに深まっていった。
こっそり盗んだ姉の下着は、度重なる自慰により精液で無惨に汚れた。
(もう一枚、姉さんのパンティーが欲しい)
その日は朝から実力テストのある日だったが、
塾へ向かう途中で聡史はどうしても姉の下着が欲しくなり、来た道をひき帰した。
聡史が家の近くまで戻ったとき、前を行く姉の後姿に気づいた。
(あれ、 、)
姉は一人ではなかった。
見たことのない小柄な少年が、足早な姉にまとわり付くように一緒に歩いていた。
聡史の見守るなか、二人は家に入っていった。
(姉さん、会社に行ったはずなのに、それにあいつは誰だ)
少年への姉の態度は、遠目に見てもわかるよそよそしさだった。
周囲の人に、細やかな配慮をするいつもの姉らしく見えなかった。
(もう、冗談じゃないよ)
姉の下着を手に入れたい一心の聡史は、その思いを阻まれる成り行きに苛立った。
(あいつ、ひょっとして)
聡史は数日前の、母と姉の会話を思い出した。
(なんでいじめの取材、家でするんだよ)
自分のたくらみを中断させた少年に、聡史は理不尽な怒りをぶつけた。
(一体どんな奴なんだ)
聡史は、音をたてないようにドアを開けた。
玄関には、きちんと揃えられた姉のローヒールと、
乱暴に脱ぎ捨てられた少年のスニーカーがあった。
足音を忍ばせて廊下をゆく聡史に、リビングから姉の声が聞こえた。
姉は、勤める新聞社に欠勤の連絡をしているようだった。
聡史が廊下から、そっとリビングをのぞくと、
庭が見えるサッシにはカーテンが閉められたままで、部屋の照明がついていた。
カーテンに向かい、こちらに背中を見せて、姉は携帯電話を片手にしていた。
その手前で、どう見ても中学生と思える少年がソファにふんぞり返り、
『つばさの会』の案内書をめくっていた。
それは新しく刷り直したサンプルを母が持ち帰り、
テーブルの上に置いていたものだった。
聡史は、たとえようのない違和感を覚えた。
リビングの様子も、姉も、そして少年も、普通ではなかった。
(なんで姉さん会社を休むんだ)
聡史は、少年に目を向けた。
(なんだよ、こいつの態度の大きさは)
携帯電話を切っても姉は、カーテンの前に立ったままだった。
少年は『つばさの会』の案内書を丸めて持ってきたリュックに入れると、
真紀の背中に顔を向けた。
「白石さん、もう済んだのなら、こっちへ来なよ」
しばらくじっと佇んでいた真紀は、
さっと身をひるがえし、毅然として少年に歩み寄った。
「もし約束を破ったら、
その時は、あなたを殺して私も死ぬわっ」
「おっかないなあ、約束は守るよ、
あのとき撮ったビデオ、これも返すよ」
少年はリュックからビデオテープを取り出し、テーブルの上に置いた。
「これでいいでだろ、だからさ、始めるよ」
少年がソファから立ち上がった。
聡史は不安と恐怖につつまれた。
(どうなってるんだよ)
約束、 、死ぬ、 、殺す、 、
聡史は確かに、そんな姉の言葉を耳にした。
ビデオ、 、という少年の言葉も。
(姉さんのあんな恐い顔、はじめて見た)
聡史は、これからいじめの取材が行なわれると信じて疑わなかったが、
その場の雰囲気が、尋常のものではないことに慄いていた。
真紀はすこし顔を上にして目を閉じた。
リビングをのぞく聡史に、姉と少年が向かい合う姿が見えた。
(姉さん、なんて綺麗なんだ)
混乱した頭のなかでも、聡史は姉の美しさに心を奪われた。
その聡史の目の前で、
少年が、真紀のサマーセーターのふくらみに両手をそえた。
(あっ、姉さんっ)
一瞬、わずかに肩を引いただけで、真紀は静かに目を閉じたままだった。
聡史はおもわず声が出そうになったが、
あまりの出来事に全身が麻痺したようになった。
少年の手に力が加えられ、ふくらみの形がいびつに変えられていった。
聡史には理解できなかった。
そして目の前の光景が信じられなかった。
「一週間ぶりだね、
へへっ、あのとき白石さんが処女だったんでビックリしたよ」
真紀がまったく抵抗しないことに調子づいた少年はぺらぺらと喋った。
「たくさん血を流してたね、
やっぱりあれかな、犯されても初めての男は忘れられないものなのかなあ」
少年は、聡史を驚愕させることを言った。
(あの日だ)
聡史は一週間前の、姉が頭が痛いと言って晩ご飯食べなかった日を思い出した。
(あの日、姉さんはレイプされたんだ)
聡史の目に涙があふれた。
(姉さん、処女だったんだ)
聡史は猛烈に腹を立てた。
(姉さんの綺麗な身体を、あいつがレイプしたんだ)
聡史はしだいに事の成り行きを理解した。
(姉さん脅されてるんだ、だからじっとしてるんだ)
少年を打ちのめそうと思った。
そして姉を救おうと聡史は思った。
動けなかった。
麻痺した身体が動かなかった。
しかし、それがいい訳であることを、聡史自身も自覚していた。
聡史は、自分が勃起していることを知っていた。
右手はすでに、ズボンの中へ潜りこんでいた。
姉の真紀がレイプされた事実を知った瞬間、
痺れるような興奮で、自分のペニスがいきり立ったことを聡史は知っていた。
自分の大切な人が汚されていく残酷な陶酔感に、聡史は身を委ねた。
あの少年への怒りも、口惜しさも、本物だった。
また、姉への愛情と憐憫も、本当の物だった。
ただ聡史にとって、美しい姉が墜されていく姿は、何よりも刺激的だった。
聡史は泣きながら、
それでも両目を見開いて、自分のペニスをこすり続けた。
「白石さんて呼びかた、よそよそしいな、
真紀って呼んでもい