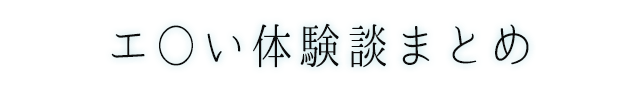妻が浮気しることは薄々感づいていたが、ついにその確信を得た。それは節分が過ぎた寒い朝だった。私が出勤しようとしていた時、突然、電話が鳴り響いた。受話器をとると、それは妻の上司の課長からだつた。電話には妻が出ると思っていたらしく、私が出たので課長は驚いた様子だった。
電話を妻に代わった。二人が話している内容は、取るに足らぬ私的な用件だと思い、嫌な感じがした。それは妻の日頃の口ぶりから、妻と課長との間は深い関係に進みつつあることを薄々感じていたからだ。
その電話は、逢う約束をする電話ではなかったかと邪推した。そんな邪推から私は妻に「急な用件でない限り、出勤してから云えばいいことであって、出勤前のこんな時間に家に電話するとあらぬ誤解を招くよ…」 と注意すると妻は、(気づかれたか…?)と思わせるような不安な素振り見せた。たまたま今朝は、私が居たからわかったことで、いつも、この時間に、まだ家にいる妻に電話して連絡を取っているのではないかと思った。
その日、一日中そのことが気になっていた。嫉妬すると余計に妻が恋しくなる。今は車社会なので、車であれば、車の中でもたやすく愛し合うことは出来るし、また、車が容易に乗り入れ出来るラブホテルは、人目を避けた川沿いなど、あちこちに立ち並んでいるのだ。何処でも短時間に愛し合い、愛し合った後は平常心で帰宅しておれる。自分も彼女を誘ってそのような浮気をしている体験から、妻もそんなことに誘い込まれているのではないか、そんなことが頭をよぎった嫌な一日だった。
気にしながら帰宅したその夜、私は、布団に横たわった妻に手を差し伸べた。すると妻は、すかさず「今朝はごめんなさい…」 と言って私に寄り添ってきた。つい私も「いいのよ…、勤めていると、つい仕事のことで深入りすることはあるからね…。気にしなくてもいいのよ…、それより、上司に仕事もだけど、女としても可愛がられることだよ…。人から好かれない女は、誰も好きになれないから…」と云っていた。妻はその一言に、心から掬われたかのように、涙ぐんだ声で「ごめんなさい…」と言って再び私に抱きついた。その仕草が、愛しかった。
その時私は、妻の詫びる素振りを目の当たりにして、確証はないものの、やっぱり二人の関係は、男と女の中にまで進んでいる、と思った。その頃の私は、週末土曜日にしか妻を求めていなかった。それにもかかわらず妻は、それを素直に受け入れてくれず、「イヤ、その気になれないの…」とか云って必ず拒んだ。なおも欲求すると、妻は嫌々ながら、人形のように身体だけを投げ出して、早くすませて…と云わんばかりに、無反応に応じてくれることが多かった。
その夜の妻は、私の誘いに拒むことなく、私の差し出す手を素直に受け入れた。しかもいつもは、私に背を向けて横たわるのに、その夜の妻は仰向けに寝て、あたかも私の誘いを待っているかのような姿勢を取っていたのだった。不倫していることを心から詫びているのだと私は思った。
私も妻に隠れて浮気していることから、妻だけ責めるわけにいかない。直すのなら自分の浮気も綺麗にすべきだと思ったし、また、妻と課長との真実を知ることは怖かった。不問に付すのが妻への愛情かとも思った。
私が妻に足を絡ませると、妻は積極的に私に抱きついてきた。これまでになかった妻の積極さだ。その仕草は、課長との関係が薄々知れたことに強く反省し詫びているようにも思えた。彼女から浴衣の前を拡げて抱きつき、珍しく私の怒棒を探り求め、唇にもあててくれた。彼女が主導権を握って騎乗位で揺さぶってくれるなど、彼女の積極的な躯の動きでも、妻が誠心誠意私に尽くして、心から詫びていることが感じ取られた。
私は正常位に覆い被さって、抱きしめた真下の妻の顔を見つめて律動を繰り返した。妻がからだを捩り、快感に歪むその顔を見ながら、課長の硬いものをここに受け入れて、このように乱れた顔をしたのではないか、と思ったら急に嫉妬心が沸いて、妻をこれ以上に快感の極限に追い込んでやろうと思った。
私は、正常位からからだを外して妻の両脚を拡げた。下半身が豆電球のオレンジ色の光に曝し出され、四十二歳熟女の茂みが丸見えとなった。艶やかな秘部はねっとりと濡れて光っていた。
その秘部に唇を寄せて、秘部を覆っている茂みを舌先でかき分けると、肉襞の奥に割れ目の存在を舌先に感じた。厚い肉襞が次第に膨らんできて、割れて拡がり、朱色に染まった薄い肉襞が現れた。舌でその薄い肉襞を舐め上げた。柔らかかった。とろりと粘液が口の中に拡がった。
割れ目に尖らせた舌を差し入れと、その割れ目はすっとうねりながら閉じてしまう。下腹部の動きと、太腿の白い柔肌とも違ううねり方をし、ここだけ別の生き物みたいだ。
尖った舌先が妻の最も敏感な芽を強く突っていた。 「アァ…そこはダメ…」 腹の底から沸き上がるような呻き声があがって、からだが硬直した。粘液にまみれている芽を舌先で弾いた。下腹部全体が大きく跳びはねるように波を打つ。白い指が布団の淵を掴んで、その強烈な刺激から逃れようと、腰と太腿を凄くばたつかせた。
私は、敏感な芽を掴んだ唇は離さない。「アッ…」 妻の腰の動きが更に激しくなった。舌と唇がずれないように動きを合わせた。すると襞に隠れている艶やかな芽がすっかり姿を現した。強烈な刺激に女のその包皮がすべて剥けてしまったのだ。
「もうダメ…」絞り出すような甲高い声が放たれた。鼻筋の通った整った妻の顔が歪んだ。妻が顔を左右に激しく振って絶頂にあることを訴えている。額から汗が流れ、髪が乱れ、ほつれた。妻も時にはこんなに凄く感じるものかと、その激しい妻の昂ぶりに私は驚いた。
予期せぬ妻の凄い反応だった。妻はグッタリとして放心状態になった。疾走した後の呼吸のように吐く息が大きく激しく、その吐息の音が色っぽかった。それを見た私は鋼鉄のような男塊を妻の肉襞に貫き、激しく妻の身体の奥を突いて、溜まっていた精液のすべてを妻の子宮に注ぎこんで果てていった。私の鋼鉄を呑み込んだ妻のそこは、数秒おきに膣の筋肉が大きく収縮を繰り返して男塊を強くを締め付けていた。私はどのくらい繋いでいたのだろうか。妻の膣の大きな収縮も治まり下腹部の痙攣も治まって、呼吸もだんだん静かになった。萎んでいく男塊を抜いた。妻は死んだように動かなかった。
久しぶりに見た妻の激しい反応だった。妻も時にはこんなに激しく揺れるものかと改めて感じた。妻が他の男を密かに思い焦がれて、その男との性欲に溺れていくのも女の人生の一齣だ。ただ、その真実を知らされるのは怖いし聞きたくもない。するのなら家庭を壊さないように、夫にわからないようにして欲しいし、時には今夜のように凄く乱れて欲しい。自分も妻に隠れて浮気しているのだから…と自戒の心もあった。横たわる妻が、失神したように、身動きもせずに大きな吐息して横たわる寝顔を見ながら、私は、妻と課長との事には触れず不問に付すことにしようと思うのだった。