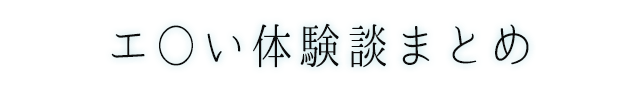涼水玉青は渚砂のベッドに潜り込み、枕に顔を埋めた。
「すーはー、すーはー」
渚砂の残り香を胸一杯に吸い込み、玉青は光悦とした表情を浮かべる。
今、渚砂は空き部屋で静馬と情事の真っ最中のはずであり、この部屋は玉青だけの領域なのだ。
匂いを堪能した玉青は、ベッドから降りて渚砂の箪笥に手を伸ばす。引き出しを開けると、そこには色取り取りの下着が詰め込まれていた。
「はあ……はあ……」
玉青は荒い息を吐きながら、敷き詰められた下着の中から小さなピンクのリボンの付いた純白のショーツを取り出した。
(渚砂ちゃんの、渚砂ちゃんのパンツ……。た、堪りませんわ!)
興奮と緊張で震える手を動かして、玉青はパジャマと下着を脱ぎ捨て全裸になり、渚砂のショーツに足を通す。
扉の鍵はしっかりと閉めてあるので有り得ないが、もし誰かに見られたらと思うと、玉青の心臓は一層高鳴った。
ドキドキしながらゆっくりとショーツを引き上げていく。
布地が無毛の秘裂に達すると妖しい快感が押し寄せてきて、玉青は秘部から愛液がトロリと漏れ出てくるのを感じた。
次に渚砂のブラを着けてみる。サイズが小さいので着ける事が出来るかどうか心配だったが、多少苦しいもののなんとか大丈夫のようだった。
最後に渚砂の制服を着込むと、玉青は自分自身を抱きしめるように腕を交差させて両肩をギュッと掴んだ。
「ああ、私の渚砂ちゃん……渚砂ちゃん!」
イケナイ事をしている背徳感と、渚砂の衣服に身を包まれている幸福感に、玉青はぷるぷると身を震わせた。
(このまま外に出ればもっと気持ちよくなれる気がしますわ!)
感極まって慌ただしく扉を開け放ち、廊下に飛び出す。その途端、部屋の前を歩いていた人影とぶつかり、玉青は尻餅を着いた。
「いたたた……」
「だ、大丈夫?」
強かに打ちつけたお尻を痛そうに擦る玉青に、ぶつかった相手は心配そうに声を掛けてきた。相手の方は、衝突の後にステップで体勢を立て直したため転倒を免れたようだった。
「立てるかしら? 怪我はない?」
優しく気遣ってくれるその声に聞き覚えがあり、玉青はハッとして顔を上げる。
「ち、千華留様……」
目の前にいる人物は、ル・リムの生徒会長、源千華留だった。下級生達の間でアストラエアの聖母と呼ばれて親しまれている、ル・リムの至宝だ。玉青の美少女チェックノートでも最高ランクに位置づけられている。
「玉青ちゃん、大丈夫?」
「あ、はい」
玉青は千華留が差し伸べた手を握ってゆっくりと立ち上がった。
渚砂の服を着ている後ろめたさから、玉青は無意識に少しでも服を見られまいとして、手を胸元に置いた。
「ん……?」
秘密部部長である千華留の並外れた観察眼がそんな些細な仕草から何かを感じ取ったのか、千華留はじぃっと玉青を見つめた。
「んん……?」
さらに、毎日のように様々な衣服を作っている変身部部長としての直感からか、玉青の着ている制服に違和感を覚えたようだった。
「な、なんでしょうか?」
不審に思われていることを察して、玉青は顔を引き攣らせている。
「ごめんなさい、なんでもないわ。それよりお尻、大丈夫? 痛くはない?」
「は、はい。もう大丈夫です」
「そう。でも念の為、薬を塗った方がいいわね。私の部屋に塗り薬があるから、一緒に行きましょう」
「え? で、ですが……」
勘の鋭い千華留を警戒している玉青に、千華留は優しく微笑みかける。
「いいからいいから。玉青ちゃんとは一度ゆっくりお話ししたいと思っていたし。もう詮索もしないから、ね?」
聖母千華留が嘘を付く筈がない。千華留の言葉に玉青は安心してコクリと頷いた。
先に千華留が部屋に入り、玉青を招き入れる。
「ここが私の部屋よ。さあ、入って」
「はい。失礼します」
「変な所を漁ったりしちゃ駄目よ?」
「ご安心ください。千華留様自作の百合小説をベッドの下から掘り出したりはしませんので」
「なんでそれを知ってるのっ!?」
「え? 本当に有るんですか?」
「じょ、冗談だったの? ……あ、ちが、今のなし」
千華留はフルフルと頭を横に振った。
「そんなのあるわけないじゃない。冗談よ。玉青ちゃん、信じちゃったの?」
「…………」
「ほ、本当よ? ル・リムの生徒会長である私が、夜な夜なこっそりとそんなものを書いているはずがないでしょう? ありえないことよ。なんなら調べてみる? あ、で、でも、何も出てこないから意味はないわよ? 無駄な徒労に終わるだけね。お勧めはしないわ。やめたほうがいいわね。うん、やめなさい。というより、お願いだからやめて下さい」「千華留様、もう分かりました。分かりましたから……」
「そう。分かってくれればいいの。えっと、あれ? ごめんなさい、私ちょっと混乱してて。何のために二人で私の部屋へ来たのだったかしら?」
「ですから百合小説の??」
「その話は終わったの!」
「あら、間違えましたわ」
「本当に!? ワザとやってない!?」
「とんでもありませんわ」
「全くもう……。ああ、そうそう。思い出した。塗り薬ね。玉青ちゃん、そこのベッドに腰掛けてちょっと待っててくれる?」
「はい」
千華留が棚から救急箱を取り出して、塗り薬を探し始める。
その間に言われた通りベッドの淵にちょこんと座った玉青は、千華留の後ろ姿をぼんやりと見つめた。
(ル・リムの聖母……。千華留様がそう呼ばれて慕われている訳が少しだけ分かった気がしますわ)
まさか本当に百合小説がこの部屋にあるはずはない。玉青の緊張を解すために、千華留は道化を演じてくれたのだ。
玉青は千華留の気遣いに頭が下がる想いだった。
そもそも、体当たりをかましたのは玉青の方であるにも拘らず、これほど親身になってくれるだけでも充分に優しいと言える。
しかしそれだけではなく、玉青の着ている制服に思う所がある様子だったのに、全く何の言及もしないでさえいてくれた。
普通なら、問い詰めるとまでは行かなくとも、ちょっと聞いてみるくらいはしてしまう所だろう。千華留はそれすらも玉青を困らせることになると察して、自制してくれたのである。思い遣りの心もここに極まれりといった感じだ。
千華留の優しさに触れて、玉青は胸が暖かくなったような気がした。
「あったわ。多分これね」
程なくして千華留が玉青を振り返って近づいて来た。手には塗り薬の入っているチューブが握られている。
「あの……今、多分って言いませんでしたか? 本当にそれ、打ち身用の塗り薬で合ってます?」
「ん、ちょっと種類が多くて分かりにくいのよ。でもこれだと思うから大丈夫よ……多分」
「また多分って言いましたわ!」
「大丈夫大丈夫。細かいことを気にしすぎよ、玉青ちゃん。それより??」
千華留が満面の笑みを浮かべて言葉を繋ぐ。
「折角だから、これ、私が塗ってあげるわ。うつ伏せになってくれる?」
「…………」
どうやら先ほどは千華留をいじくり過ぎたようだった。早速反撃に出てきたのだ。
しかし、玉青はそんな千華留に見惚れていた。
小悪魔的な笑みを浮かべている千華留の姿は余りにも魅力的だった。優しく相手を包み込む聖母としての側面を垣間見た直後だけに尚更だ。
「はい、千華留様」
玉青は無意識のうちに返事をしていた。
千華留にスカートを捲り上げられて、ベッドの上でうつ伏せになっている玉青のショーツが露わになる。
つい千華留の魅力に翻弄されて承諾してしまった玉青だったが、激しい後悔に襲われていた。
お尻に薬を塗ってもらうなんて恥ずかしい、という考えにようやく辿り着いたのだ。
しかし今更逃げるわけにも行かず、玉青は頬を染めて羞恥に耐えている。
「あ、あら?」
しばらく玉青の下着をうっとりと眺めていた千華留が、不意に戸惑いの声を上げた。「どうしました?」
「……別に、なんでも、なんでもないわ」
明らかにうろたえている千華留の様子に、さすがに玉青は不安になった。
少し考え込んで、玉青は一つの可能性に行き当たり、慌てて身体を起こして下着を確認した。
「渚砂ちゃああああんっ!」
予感が当たり、玉青は思わず絶叫した。
渚砂の下着を愛でている時は興奮の余り全く気付かなかったが、下着にバッチリ『蒼井渚砂』とマジックで書かれていたのだ。
寮の規則で下着に名前を書くことにはなっている。けれど、一年生ならともかく、四年生にもなってそんなことを守っている生徒はまずいない、はずだった。
編入生である渚砂はそんなことは知らずに、せっせと下着に名前を書き込んでいたのだろう。
「あ、あの、千華留様……」
言い訳をしようとして玉青は顔を上げた。千華留は呆然として固まっていた。
玉青はこれから自分がどうなるか分からず、気が遠くなりそうだった。最悪の場合、シスターに報告されてしまうかも知れない。そうなれば、渚砂にもバレてしまうだろう。
恐る恐るもう一度玉青が声を掛けようとした時、突然千華留が親指をグッと突き出した。
「ナイスよ玉青ちゃん! 常日頃から変身しているなんて恐ろしい才能だわ!」
目を輝かせた千華留が正面から玉青の両肩を掴む。
「玉青ちゃん、変身部に入らない?」
「え、えっと……変身部?」
「そう。私の作った衣装に着替えて変身する部よ。玉青ちゃん程の逸材なら即レギュラー間違いなしよ!」
「で、でも私、文芸部に入っていますので……」
「そうなの? でも大丈夫よ。我が部は掛け持ちもオッケイだから」
「あ、で、では、よろしくお願いします」
助かったことを悟った玉青は、安堵の余り思わず変身部への入部を受け入れてしまった。けれど不思議と後悔はない。千華留と一緒に居られるのならそれも悪くない、と玉青は思い始めていた。
「玉青ちゃんの隠れた才能については誰にも言わないから安心してね」
「は、はい。ありがとうございます」
「それに実は私も、詩音さんの制服をこっそり着てみたことがあるのよ」
「詩音さん? どこかで聞いたことがある名前のような……」
「冬森詩音。スピカの生徒会長のことよ」
「ああ……あのデコッパチですか」
「た、玉青ちゃん?」
「あら、口が滑りましたわ」
「滑り過ぎよ!」
「冗談です」
もう一度うつ伏せになり、玉青のスカートが捲り上げられる。渚砂のショーツもするすると膝まで引き下ろされ、染み一つないお尻が丸見えになった。
玉青は恥ずかしさの余り顔を真っ赤にしている。
「ジッとしててね、玉青ちゃん」
塗り薬をたっぷりと浸けた千華留の掌が、玉青のお尻に接触する。
「あ、あう。つ、冷たいです」
冷え切った薬の感覚に玉青が声を上げた。
「我慢してね。すぐに慣れると思うから」
千華留は優しく玉青の臀部全体に手を這わせて塗り薬を広げていく。
「あっ……ん……んん……」
千華留の言う通り、塗り薬の冷たさにはすぐ慣れたが、今度は千華留の手の感触が気になってきた。
くすぐったいのを堪えて身をよじるのを我慢しているうちに、玉青の口から少しずつ嬌声が漏れ出す。
繊細な手付きで何度もお尻を撫で回されると、秘裂がじんじんと疼いてくるのだ。
このままでは思わぬ痴態を晒しかねなかった。一旦手を止めてもらおうと、玉青は首を捻って肩越しに千華留を仰ぎ見る。
「…………」
扇情的な光景が目に入り、玉青は言葉を失った。千華留が頬をポウッと赤く染め、夢中になって玉青のお尻に薬を塗り込んでいたのだ。
「ん? ど、どうしたの、玉青ちゃん?」
「あ、いえ。なんでもありませんわ」
玉青は慌てて誤魔化しながらも、千華留から目を離すことができなかった。
(聖母千華留様が私のお尻を触って興奮して下さるなんて……)
だんだんと実感が湧いてくると、同時に嬉しさも込み上げてくる。もっと千華留に喜んでもらいたいと心の底から思った。
玉青は今まで迷惑を掛けた分を取り戻すつもりで、勇気を出して誘いを掛ける。
「千華留様、あの、お股の方も塗ってもらえますか? そこも打ち付けてしまったような気がしますわ」
言われた通りに千華留は玉青の股間に手を滑らせる。
「玉青ちゃん、こ、このへん?」
「もっと、もっと下です……ひゃうんっ」
秘部に千華留の指が当たって快感が走り、玉青の身体がビクンと跳ねる。
「そのへんです、千華留様。その辺りに一杯塗り付けて下さいっ」
「わ、わかったわ」
玉青の恥部が千華留の掌でピタリと蓋をされた。千華留はゆっくりと手を上下させて、玉青の秘唇を擦り上げていく。
掌に刺激された淫部から愛液が流れ出て、塗り薬と混ざり千華留の手を濡らす。
「あふっ……はあ……あっ……」
くすぐったいような気持ち良いような弱々しいタッチに翻弄され、玉青は嬌声を抑えることができなかった。
次第に気持ちが上り詰めて来るのを感じて、再び首を捻り千華留に視線を向ける。今度は千華留の手を止める気はない。ただ千華留の顔が見たくなったのだ。
顔を上気させて夢中で自分の柔肉を擦ってくれている千華留を見て、玉青は愛おしさで胸が一杯になった。
玉青の視線に気付き、千華留が動きを止める。
「な、なに? 玉青ちゃん」
「あああ、千華留様、手を止めないで下さい」
「ご、ごめんなさい」
慌てて愛撫を再開する千華留。
途端に玉青の下半身へ快感の波が駆け上がってくる。
「も、もうイキそうですわ。イッてもいいですか?」
「いいわよ。玉青ちゃんのイクところ、私に見せてちょうだい」
「ん、あ……イキますっ!」
玉青の身体がビクビクと痙攣する。
淫裂から愛液が噴出して、秘唇を塞いでいる千華留の掌に次々と当たった。
玉青の艶めかしい蜜が千華留の手の平から漏れて、トロトロとシーツの上に流れていった。
「本当に可愛いわ、玉青ちゃん」
絶頂を終えてぐったりしている玉青の頭を、千華留が優しく撫でる。
「んん……」
玉青は心地良さそうに目を閉じて余韻に浸っていた。
ひとしきり穏やかな時間を堪能した後、玉青は千華留にも気持ち良くなってもらおうと思って口を開く。
「千華留様、ぶつかった時に怪我などはされませんでしたか?」
「ん? 私は大丈夫よ。倒れたわけではないし」
「そうですか? 本当に? 私とぶつかったところが痛んだりはしませんか? 特に胸とか」
「…………。そういえば、ちょっと胸の辺りが痛いかも。特に乳首とか」
「やはりそうですか! では、今度は私が千華留様に薬を塗って差し上げますわ」
「う、うん。ありがとう、玉青ちゃん」
寝そべっていた二人はベッドの上でお互いに向き合って座り直す。
玉青が千華留のパジャマに手を伸ばし、プチプチとボタンを外していくと、千華留は顔を赤くして恥ずかしそうに視線を逸らした。
「そんなに強張らなくても大丈夫ですよ、千華留様」
一度絶頂を迎えてどこか吹っ切れた玉青とは対照的に、千華留は小刻みにプルプルと震えて緊張しているようだった。
「た、玉青ちゃん、優しくしてね」
「もちろんですわ」
玉青はボタンを全て外し終え、千華留のパジャマをはだけさせた。ピンクの可愛らしいブラジャーに包まれた量感のある隆起が露わになる。
「大きくてとても素敵な胸ですわ、千華留様」
「そ、そう? その、ありがとう」
恥ずかしがる千華留が、玉青にはとても可愛らしく思えた。
「では失礼して……」
ブラジャーを押し上げると、玉青の目の前に千華留の乳房がプルンと飛び出してきた。
ツンと硬くなっている乳首を見て辛抱堪らなくなった玉青は、慌てて親指と人差し指に薬を塗り、千華留の乳首を摘まみ上げる。
「はうっ」
千華留がビクリと反応する。
「薬を、薬をもっと良く塗りませんと……」
目をギラギラさせながら、玉青は千華留の乳首を摘まんだまま弄る。
「あ、んん……玉青ちゃん……ああ……」
「可愛いですわ、千華留様っ」
感極まった玉青は、勢い良く抱き付いて千華留の上体を押し倒した。
ベッドに仰向けに倒れ込んだ千華留の上に、玉青が覆いかぶさる。
「もっと気持ち良くして差し上げますわ」
「た、玉青ちゃん」
「よろしいですか? 千華留様」
千華留が小さくコク、と頷いた。
すぐに玉青は千華留の乳首に顔を寄せてパクリと口に含む。チューチューと乳首を吸い立てると、千華留が快感に打ち震えて仰け反った。
さらに乳首を舌で転がすように弄びながら、千華留の腹に手を置き、ツツーと股間に向かって滑らせていく。ショーツの中にスルリと手を潜り込ませ、恥毛を掻き分けて淫部に触れる。玉青は自分がそうされたように、ゆっくりと繊細なタッチで千華留の秘部を撫で回した。
「あっ……はあっ……」
声を抑えきれずに身悶える千華留。
玉青は乳首から唇を離して、嬌声を上げている千華留の口をキスして塞いだ。
「ん……」
千華留の舌を絡めとろうと、玉青は積極的に舌を差し込む。それに応えようとして、千華留も遠慮がちながらも舌を突き出してきた。
お互いの舌を絡め合いながら、玉青はなおも千華留の淫部をまさぐり続けている。
だんだんと鼻息が荒くなってくる千華留に、そろそろ絶頂を味わってもらおうと、玉青は千華留の唇から口を離した。
「千華留様、ちょっと失礼します」
玉青は、仰向けになっている千華留の足元にひざまずいてショーツを引き抜いた。
そして両足を持ち、千華留の胸に押し付ける。
「膝裏を手で持って足を固定してくださいますか? 千華留様」
「わ、わかったわ」
完全に主導権を奪われている千華留は、玉青の言う通り左右の手で自分の膝裏を掴んで足を抱え込む。
玉青はさらに千華留の腰を持ち上げて秘部を上向きにさせた。千華留は成す術もなくマングリ返しの格好を取らされる。
「た、玉青ちゃん、こんな格好はちょっと……」
「恥ずかしがる事はありませんわ、千華留様。どうか身も心も解放なさってください」
「そ、そう言われても……あうんっ」
千華留の顔から目と鼻の先で晒されている恥部を玉青が舐め上げた。
「すぐに姿勢のことなんて気にならなくなる様に、気持ち良くして差し上げますわ」
目の前で喘いでいる千華留の顔を見ながら、玉青は薄い繊毛の生えている花弁を一心不乱に舐め回し始める。
「あん……ああっ……」
部屋には千華留の嬌声だけが流れていく。だがしばらくすると、止め処なく溢れてくる愛液と玉青の唾液が混ざり合い、ピチャピチャと淫らな音がするようになった。
びしょ濡れになった秘裂は一層舐めやすくなり、玉青の舌に刺激されて次々に蜜が漏れ出てくる。
玉青はさらに舌を伸ばして、クリトリスをひと舐めした。
「きゃうんっ!」
突然の刺激に、千華留は思わず全身をビクビクと波立たせる。
「どうやら千華留様はここが弱いようですね。では、お豆さんを重点的に攻めさせて頂きますわ」
千華留は何かを言おうとしたが、口を開く前に玉青が再び肉豆を舐め上げた。
「はああっ」
口端から一筋の涎を垂らしながら、千華留は強烈な快感に喘ぐ。
玉青がクリトリスに舌を押し当ててグリグリと擦りつけると、千華留の体がガクガクと震え出した。
「あ、ああっ!」
いきなり千華留の秘奥から潮が噴き出した。
「あう」
顔面にほとばしりが当たり、玉青が反射的に顔を引く。
天井に向かって二度三度ビュッビュッと放出が続き、絶頂の蜜は千華留自身の腹にポツポツと落ちていった。
玉青はもう一度顔射を受けてみたかったが、既に勢いが弱まっておりそれは難しそうだった。代わりに千華留の秘部のすぐ上に手の平をかざしてみる。期待通り、最後の噴出が掌に当たり、玉青は笑みを浮かべながら粘液をねぶった。
「ご、ごめんなさい、玉青ちゃん。顔に当たっちゃったわよね?」
千華留がマングリ返しの姿勢のまま申し訳なさそうに言った。
「いえいえ、お気になさらずに」
対して玉青の方は、一浴びだけとはいえ初めての顔射を経験できてご満悦だ。
千華留の足を下ろしてやり、玉青はティッシュを取り出して千華留の腹を拭き始める。
「あ、自分で拭くから大丈夫よ、玉青ちゃん」
「いいんです。やらせてください。だって千華留様、とっても可愛いんですもの」
「そ、そう?」
「可愛すぎて、千華留様というより、ちかるんといった感じですわ」
「ちかるん……? いいわね、それ。これから私のこと、そう呼んでくれる?」
「はい。もちろんですわ」
早朝、千華留と共に一夜を過ごした玉青は、渚砂の制服と下着を身に着けて、そろそろ自室に帰ろうと身支度を整えていた。
「朝早くから慌ただしくして申し訳ありません、ちかるん。渚砂ちゃんが寝ている内に帰りませんと、色々と問題がありますので……」
「そうね。変身部入部を電撃的なサプライズにするためには、まだ玉青ちゃんの変身の才能は隠しておいたほうがいいわね」
「は、はあ。……もっとも、渚砂ちゃんもまだ静馬様の部屋にいるかも知れませんが」
「玉青ちゃん、その、静馬様のことは……」
「大丈夫です。私は静馬様に対して何の感情も持ち合わせてはいませんわ」
「そ、そう……」
「はい。全く何の遺恨もありません。皆無にして絶無です」
「……」
「しかし、偶に、本当に極偶にですが、もし静馬様がいなければ、と思うこともなくはありません」
「……」
「そう、そうですわ! 静馬様さえいなければ……fuckyou! ブチ殺すぞ静馬!」
「た、玉青ちゃん?」
「あら、地が出てしまいましたわ」
「地!? 今の地なの!?」
「冗談です」
「どのへんから!?」
「ちかるんと廊下でぶつかった辺りからでしょうか」
「そんな最初からなの!?」
「それはともかく、本当に大丈夫です。私は、渚砂ちゃんが幸せなら、それで……良いですわ」
「玉青ちゃんは強いわね。でも、寂しくなることもあるでしょう?」
「……はい」
「その時はまたいつでもここに来てね?」
「はい」
「部活もね。変身部のみんなもきっと大歓迎よ」
「はい」
「絆奈ちゃんも檸檬ちゃんも籠女ちゃんもね」
「はい」
「絆奈ちゃんと玉青ちゃんの声って似てるわね」
「似てません」
「そ、そう?」
「はい」
「何にしても、玉青ちゃん。変身部の新入生歓迎会、楽しみにしててね」
「はい!」
玉青は満面の笑みを浮かべて頷いた。