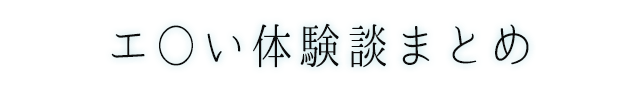(可愛いわね…)華奢な体つき、細い手足、そして一見少女と見まごうほどの中性的な顔立ちと白く若い肌。
いますぐ抱きしめてしまいたくなるほどだ。
里子はうっとりとした表情で少年を凝視していた。
少年のほうは前屈みのままうつ向き、顔を真っ赤にして固まったままだ。
前屈みといういう事は早くも勃起しているということなのだろう。
(こんなおばさんの体でも、こ、興奮しちゃうの?)里子は戸惑いと恥じらい、そしてほんのわずかだが女としての悦びを感じていた。
14才の少年が37才の人妻の自分に欲情しているのを感じると、女としてのプライドを充分刺激された。
里子にとって目の前の少年が性的なものにいかにも不慣れな立ち振舞いは充分に微笑ましく、里子が笑みを浮かべさせるに充分であった。
少年はいまだに固まったままうつむいている。
今は少年を落ち着かせ、そしてコミュニケーションをとることが先決であった。
里子は少し考え、話し始めた。
「タクミ君、サッカーとか、野球とか、興味ある…?」
里子は世間話をはじめた。
とりあえず、この世代の少年なら乗ってくる可能性が高いと思われるスポーツの話題からはじめた。
目の前の少年はスポーツに興味があるらしく、里子の振った話題に少しずつ乗ってきた。
中でもサッカーと野球の日本代表の話題ではある程度盛り上がることが出来た。
やがて話はお互いの趣味や私生活にまで及び、二人の間にあった何かが取り払われていった。
そして少年の顔が徐々に明るくなっていき里子のほうを見るようになってきた事に里子はホッとした。
里子は少年がようやく和んできたのを見てホッとした。
さらに会話を続けているうちに、少年の緊張が少し和らいだのか、視線が里子の顔だけではなく、豊満な胸の膨らみや量感あふれる太ももへと移動するようになったが、里子は気がついていない振りをした。
里子は自分の体を少年の視線がチラチラと這うのに任せていた。
(ふふ、可愛いわね)里子は少年と会話しながら心の中で笑顔を浮かべた。
少年は自分がどこを見ていたか悟られぬよう、視線を泳がせ誤魔化していた。
愛らしいことこの上なかった。
里子は、いかに幼い少年であっても性的興味のこもった視線で見つめられては羞恥をおぼえてしまう。
(も、もしかしてこの子…)独身時代、高校時代に初体験を終えて以降、様々な男たちと交わってきた。
結婚してからも仕事ばかりで家庭を省みず、かまってくれない夫に不満を募らせ、ついには知り合いから教えてもらった出会い系サイトで知り合った数人の男性と割り切った関係を続けてきた。
そんな里子にとって今の少年の様子、とりわけ里子の体にせわしなく視線を送る様は全く女慣れしていない男の、女体に対する異常な興味を示しているようで今まで会ってきた性の経験がある男達とは明らかに違う。
もちろん思春期を迎えたばかりの少年特有の興味というのもあるのだろう。
里子ある事を考え、思いきって少年にたずねてみた。
「タクミくん」
「はい…」
少年はハッとして里子を見つめた。
「タクミ君は…その…」
なかなか言葉に出来ない。
しかし里子は勇気を振り絞って聞いた。
「セ、セックスしたこと…あるの?」
恥かしげに小さく首を振った。
(やっぱり…)里子は無垢な未経験の少年であるということをはっきりと認識し、間髪入れず里子は質問を浴びせる。
「そ、そう…じゃあ、女の子と、キスをしたことは?」
少年はまた、小さく首を振った。
おそらく自分の未熟さが恥かしいのであろう。
(こんな…可愛らしい子なのに、キスもまだなの?)里子はそういう少年相手に性の相手をしなくてはならないのだと思うと体が震えた。
大人の女の余裕など消えかかっていた。
「…好きな子とかはいないの?」
少し考え、少年は首を振った。
「そ、そう…」
「いいの?はじめてがこんなおばさんで嫌じゃない?」
そう言うと、少年が必死な形相で口を開いた。
「そ、そんな事、ないです!会った時すごいきれいな人だなって、思いました…会ってよかったなって…だから…」
「だから?なぁに?」
「あの…その…」
少年は言葉に詰まってまたうつむいてしまった。
顔を赤らめている。
「大丈夫よ、思ってる事ちゃんと言ってみて」
「……だから、僕…里子さんとしたいんです。
」
少年は素直な気持ちを告白した。
はっきりとした口調だった。
ストレートな物言いに里子はドキリとしたが少年の真摯な想いを感じ、里子の心臓は高鳴った。
「ありがとう、嬉しいわ…すごく」
「ほんと?」
そう言うと少年は顔を上げた。
「本当よ…タクミ君みたいな子に、気に入ってもらえるなんておばさんも、まだまだ捨てたものじゃないわね」
半ば本心であった。
少年の想いに、応えてあげたい。
里子はそう思った。
こをな愛らしい少年が自分を選んでくれたということが、里子の中にほんのわずかだが積極的な気持ちが芽生えさせていた。
(教えてあげたい…)少し気が楽になった。
里子は覚悟を決めた。
「タクミ君…」
少年の目を見据えながら言った。
「は、はい」
少年がどきまぎしながら返事をした。
「いっしょに…シャワーを浴びましょう」
そういわれた途端、少年の体が、ビクンと震え、しばらくしてから少年は軽くうなずいた。
二人で脱衣所までくると、里子は少年の目の前で衣服を脱いだ。
こんもりと盛り上がった茂みや乳房を隠す気はなかった。
里子は自分を褒めてくれた少年に応えるため、あえて少年に自らの大きな乳房を晒したのだ。
しかしいくら覚悟を決めたといっても、はるかに年下の少年に抱かれるという禁忌はなかなか拭えない。
(いまさら何をためらってるの?)里子は自分を鼓舞した。
少年のほうを見ると、少年はトランクス一枚になって前屈みになって真っ赤な顔を脱衣所の床に向けていた。
なぜ前屈みかは、里子にはわかっていた。
そして照れがあるのか、なかなか里子のほうを直視しようとしなかった。
ただし、やはり年頃の少年らしい好奇心には負けてしまうのか、ちらりちらりと視線を上げて、里子の乳房を盗み見ていた。
そして、乳房が視線に入るとまたうつむいてしまうのだ。
その行動が、里子にばれていないと思っているらしい。
そんな少年の行動を見て、里子は少し緊張がほぐれるのを感じた。
(初めてだもんね、仕方ないわいよね)里子はクスッと笑うと、手を伸ばして少年が身につけているトランクスに手をかけた。
リードしなくてはと思った。
「ぬ、脱がしてあげる…」
その瞬間、少年がビクッと震えて里子のほうを見る。
そして今度はまともに里子の大きな乳房を目にし、今度はゆでダコのように顔を紅潮させる。
少年の体がいっそう前屈みになった。
しかし、もう少年は視線をそらそうとはしなかった。
いや、視線をそらせないのだ。
里子の乳房にはそれだけの魅力があった。