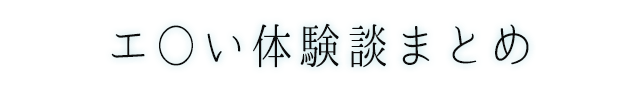T県Y市。
都心から少し離れた、人口三万人ほどの片田舎に俺は住んでいた。
今にして思えば、この地域には何もない。
中心市街地を少しでも外れて、辺りを見渡せば半分以上が畑や田んぼの光景で、近くに大きなショッピングモールや高層ビルもなく、数十メートルおきに木造平屋建ての民家が軒を連ねるだけである。
この様な退屈な環境下で、俺は高校生まで生まれ育った。
そんな当時の俺が唯一楽しみにしていたのは、恋人である遥子との関係だけだった。
遥子は幼稚園からの幼馴染。比較的家が近くで、近所にも同世代の子がおらず、なにより母親同士が同級生で仲が良かったため、俺と遥子も必然的に仲良くなっていった。
遥子は少し癖の付いたセミロングヘアーと、パッチリ二重のやや垂れ目が印象的な清楚風美人で、全体的な雰囲気がAKB48の柏木由紀に少し似ていた。
身長は低めだがスレンダーな体型で、胸も中々に大きく、良好なスタイルの持ち主だった。
遥子は優等生で頭も良く、時々勉強を教えてもらい事があった。
そんな俺と遥子は高校入学と同時に付き合い始めたが、彼女は恋愛に関してかなり奥手で、最初は手すら握らせてくれなかった。
それでも俺は諦めずに積極的にアプローチを掛け、次第に遥子も受け入れてくれ、数ヶ月もすると彼女の方から手を握ってくれる事もあった。
いつしか、手を握りながら登下校するのが当たり前の習慣となっていた。
しかし、そこから次の段階にいくのにもっと時間がかかった。
良い雰囲気になりキスをしようとしても
「恥ずかしいから、イヤ」
だの
「ごめんなさい、そういう気分じゃないの」
といって拒まれ続けた。今にして思えば当然の様に思えてくる。
遥子は元々身持ちが堅く。中学校時代から幾度となく告白されたが、その全てを断っていた。
本人曰く、
「見ず知らずの相手を好きになる訳がない」
といって振っていたそうだ。
だから俺は幼馴染の立場を利用し、高校の入学式で遥子に告白した。
「あなたの事がずっと好きでした・・・俺と付き合ってください」
自分で言うのもなんだが、俺は中肉中背で勉強も運動も並程度だが、顔だけは平均を超えていた為、少し自信があった。
それより何より、この十数年間で誰よりも遥子の近くにおり、一番親しく接して来た俺が、彼女に最も相応しい男であると心の中で自負していたのだ。
「・・・・・・いいわよ、慎くんとだったら・・・付き合ってあげる」
その至福の言葉を聞いた直後は、天にも昇る気分だった。
学校でも指折りの美人を、今まさに自分の彼女にしたという事実が、この上なく嬉しかった。
数日間はその余韻が残り、優越感に浸りまくった。
その時、俺は心の中で誓った。
一生、この娘を、遥子を大切にすると。そして、誰にも渡さないと。
だからこそ、この程度では決してめげなかった。
なぜなら、付き合いだして、遥子が手を握ってくれる様になるまで約三ヶ月を費やし。
そこから、手を握って登下校してくれるまでに、更に三ヶ月を要したのだから。
キスなど、夢のまた夢であった。
俺はそれを十分に理解し、遥子の気持ちを尊重しながら関係を続けた。
そんな状態で一年も経った頃には、遥子にも俺の誠実な想いが伝わったのか、付き合い始めた当初の蟠りや、ぎこちなさがなくなって非常に仲睦まじいカップルになっていた。
「ねえ慎くん、来月の誕生日に何か欲しいものある?」
「うーん、そうだな・・・遥子のキスが欲しいなあ・・・何て」
「え!キス?」
「うん・・・駄目かな?」
「・・・うん、分かった。その変わり、少し時間ちょうだい。心の準備がしたいの」
一ヶ月など、今までの経緯からして短いとすら思った。
そして一ヶ月、俺は人生17回目の誕生日を迎えた。
俺の家で遥子が夕飯を作ってくれる事になり、彼女を台所に迎え入れた。
この時、父親は都心に単身赴任中で、母親は地元の組合で遅くまで帰ってこない、同居していた叔母(父親の妹)は彼氏の家に泊まるとそれぞれ連絡が入り、結果的に夜遅くまで二人きりの状況になった。
「慎君は、そこでじっと待っててね。今から慎君の大好きなハンバーグ作るから」
「うん、分かった」
そう言って遥子は台所に立ち、夕食を作り出した。
俺は隣の居間からずっとその光景を眺めていた。
背中まで伸びた髪を後頭部に纏め、自前の紺色のエプロンを着こなし、料理をする姿は正に
新妻そのものだった。
スカートの裾から見え隠れする太腿やふくらはぎの、生々しい光景を見入っていた。
「あっ!いけない」
そう呟いて、遥子は上体を思いっきり前傾させ、床に落とした玉ねぎを取ろうとした。
するとスカートの中から淡いピンク色のパンツが丸見えになる。
下着はお尻の割れ目に綺麗に食い込み、色も相まって巨大な桃を連想させた。
俺の息子は一気に興奮状態になった。咄嗟に遥子の方を見るが、そんな事は知る由もなく料理を続けていた。
興奮が冷め終わり正常状態に戻ると俺は、台所へと足を運び、後ろから遥子の腰に手を回して抱き付いた。
「あー!ちょっと!邪魔だから座っててよ」
「えっ!ちょっとぐらい、いいじゃん」
「いいから戻りなさい!」
そんな風にイチャ付いていると、遥子のうなじからフローラルな匂いが漂ってきた。
どうやら俺の家に来る前にシャワーを浴びたらしく、花用のコンディショナーの香りと遥子の体臭が混じり合い、何とも言いえない雌特有の匂いになっていた。
「こらっ!いい加減にしないと怒るわよ!」
「いや、もう怒ってるじゃん」
皮肉交じりに冷静な反論をし、前のめりになって顎を遥子の肩に乗っける。
目線を下げ、エプロンの中に着ている、白のブラウスの胸元を凝視する。
そこからは程よく育った二つの膨らみが、谷間を作る光景が飛び込んでくる。
日本人女性の平均バストよりも、幾分か大きいそのサイズは、俺の息子を再び興奮状態に追いやる威力を持っていた。
それを隠そうと思い顎を肩から退けようとした時、遥子が身体を捩らせて為、胸元の縁から先程のパンツと同色の薄いピンクのブラジャーがちらりと見え、更に興奮を促した。
その興奮を抑えきれない俺はトイレに直行し、入ると勢いよく射精した。
数分後、何食わぬ顔でリビングに戻って十数分後、料理が出来て遥子が運んで来てくれた。
俺も手伝うと申し出たが、
「慎くんは主役なんだから、何もしなくていいの」
なんて良い恋人を貰ったんだとこの時、しみじみ痛感した。
そして料理も食べ終わり、遥子は台所で食器を洗い、俺は居間でテレビを見ていた。
「・・・ねえ、慎くん。これもう少しで終わるから、ちょっと待ってて」
遥子の発言が何を示してるかは、言わなくても分かった。
何せ、俺から言い出した事だ。
数分もしない内に全て洗い終え、エプロンを外し俺の隣に座ってきた。
「あ、あのさ遥子・・・俺の部屋に行かない?」
「えっ!・・・ええ!・・・わ、分かったわ」
雰囲気作りの為、場所を俺の部屋へ移動し、ベットに二人で腰掛ける。
「・・・・・・ねえ、慎くん。目を瞑ってくれる?」
「・・・わ、分かった」
遥子の言う通りに素直に従い、目を閉じて口を窄めた。
ポンッという音がどこからともなく聞こえてきた。
何の音だろうと考えていると今度は、カチッという音が小さく響いた。
次の瞬間、俺の唇を塞ぐ柔らかい感触が伝わってきた。
どうやら、さっきの音の正体はリップクリームだった様で、遥子の唇から甘いハーブの香りが漂ってきた。
最初は唇同士が触れ合うだけのキスだったが、俺はそれだけでは満足せず、遥子の口の中に舌を侵入させ、彼女の唇と絡め合わせた。
「んっ!・・・ん・・・ん・・・ん」
互いの舌が交錯し合い、唾液同士が混ざって違う味を作っていた。
次第に歯止めが利かなくなった俺は、待機中だった右手をそうっと移動させ、ブラウスの上から乳房に添わせる。
「んっ!!!」
遥子は予想外の行動に、閉じていた目を見開き驚いていた。
モミンッ!モミンッ!モミンッ!モミンッ!モミンッ!モミンッ!
俺は着衣越しに遥子の美乳を鷲掴みにし、指を激しく動かした。
遥子の豊かな膨らみは掌いっぱいに広がり、時折指の間から溢れ、瑞々しく蕩ける様な感触が弾けまくった。
「や、柔らけえー!!!」
無意識の内に叫ぶほど、生まれて初めて触る女子の、遥子の胸が最高に気持ち良かった。
「んふっ!・・・んふっ!・・・んふっ!・・・」
遥子は顔を紅潮させ、必死に我慢するが。
「い、いやぁ!!!」
やはり、耐え切れずに俺の腕を振り解き、両腕で胸を抱えながら背を向けてしまった。
俺は股間が濡れる感触し、触ってみると粘り気のある液体がズボンにまで染みていた。
遥子の胸のあまりの気持ち良さに、無意識で射精したみたいだった。
「は、遥子・・・ご、ごめん・・・キスだけの約束だったのに・・・・・・本当にごめん」
俺はその場で深々と頭を下げて謝罪をした。
「・・・・・・いいの、気にしないで・・・本当は彼女の私が、こういう事も受け入れなきゃいけないのに・・・でも怖くって、恥ずかしくて・・・ごめんね臆病な彼女で」
遥子は泣きながら謝ってきた。悪いのは全部俺なのに。
「そんな事ないよ、ごめんなお前の気持ちも考えずに、欲望任せに突っ走って」
「ううん、私の方こそ・・・次からは、ちゃんと我慢できる様に努力するね」
あんな事をしたのに、俺を一切責めずに自分の方に非があると言ってきた遥子が、一瞬天使に見えてしまった。
こうして和解した後、遥子は家へ帰っていった。
俺は口の中にまだある遥子の唾液と掌に残った乳房の感触をオカズに朝まで自慰行為に耽った。
因みに俺と遥子が結ばれるのは、ちょうど一年後の俺の誕生日であった。
続く