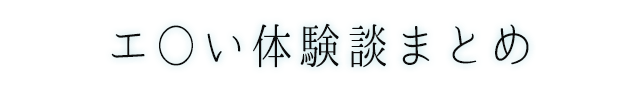俺と真紀は時にはSMチックなセックスをした。俺の部屋だと声が外にまで漏れるので、真紀の部屋かホテル、または旅行先でしていた。
そんな俺も大学4年生になって、地元に就職を決めて卒業を待つ身となった。2年間愛し合った真紀とは必然的にお別れとなる。その日が少しずつ近付いても、そのことには触れず愛し合っていた。
卒業式の後、最後の夜を真紀の部屋で過ごした。
真紀は、全裸でベッドに横たわっていた。真紀の腰の下にクッションをかませて股間の下にバスタオルを強いて、真紀を大の字にベッドに括った。目を閉じて最後の快感を待つ真紀のクリにピンクローターを当てて、ロープをふんどし状にしてローターを固定して放置した。敏感な部分に延々と与えられた振動に、真紀の腰はカクカクして、時折腹筋が筋になるほどにビクついた。中指と人差し指をマンコに入れて天井を擦りあげると、ジュピジュピいやらしい音をたてて潮を吹いた。仰け反りビクつく真紀は、やがて絶頂を迎えてグッタリとなった。
ローターを外し、拘束を解いて真紀を味わった。俺にしがみついて俺のチンポの感触を記憶にとどめようとするかのように、マンコ全体で締め付けた。
「お兄ちゃん、ああ、ああん、あああ、あっ」
二度目の絶頂を迎えようとしていたので、俺も腰の動きを早めて射精の準備に入った。ビクつく真紀に、最後の精液をかけた。俺と真紀の2年間が終わった。
翌朝、真紀は俺と一緒に帰郷すべく新幹線に乗っていた。真紀は往復切符だが、今回は俺は片道切符だった。真紀の降りる駅が近付き、乗り換えのアナウンスが流れた。
「お兄ちゃん、2年間楽しかった。ありがとう。これで、普通の親戚に戻るんだね。」
「真紀、体、大事にするんだぞ。困った事があったら、お兄ちゃんに連絡するんだぞ。」
「うん。さようなら、恋人のお兄ちゃん。」
そう言い残して、真紀は下車した。ホームを歩く真紀を新幹線が追い越した。数日後、春彼岸で本家であった真紀は、普通の従兄を見る目で俺を見ていた。俺は、普通の従妹を見る目で真紀を見れなかった。
俺は、地元育ちの素朴な田舎の娘と結婚し、平凡な暮らしをしていた。
真紀は大学卒業後も東京に残り、東京の男と結婚した。
お互い家庭を持つと、なかなか会えなくなり、お盆も本家ではなく実家へ集うようになるので疎遠になった。そして今年の3月、真紀は逝った。36歳だった。発見の遅れた悪性腫瘍は、入院僅か1ヶ月で真紀の命を奪った。
昨年、久しぶりに本家へ出向き、秋彼岸の墓参りに行った。
川のほとりに真っ赤な曼珠沙華が咲き乱れていた。遠い昔、手を繋いで曼珠沙華に囲まれたこの道を歩いた真紀は、もういない。そんなことを思いながら、川のほとりを歩ききって振り返ると、真紀が手を振っているように感じた。
「さようなら、お兄ちゃん。これで本当にお別れね。」
真紀の声が聞こえたような気がした。
今年、春彼岸には、真紀に会えなかった・・・