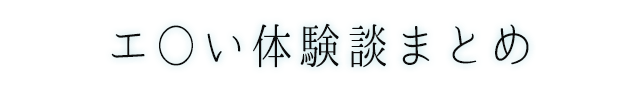私の軽はずみな行動が、まさか、こんな因果になって我が身にふりかかるとは思ってもいなかった。
私は今、後悔の念に打ち振るえ過去を呪い、自分を戒めている。
もしも、1度だけ奇跡が起こるというのなら、私は時を戻したい。
過ちを犯す前の、あの平凡な時間に。
そう・・・あの男に再会する前の日に。
あれは、新宿に買い物に出た日の事だった。
知人の結婚祝いを見立てて来るよう主人に言われ、デパートでブランドもののバスタオルセットを購入した私は、その包みを抱えて駅へ向かって歩いていた。
平日の午前中だというのに、通りは往き交う人達で真直歩く事さえ難しい。
私は包みをなるべく傷付けないよう、ぬいながら人波をくぐつていた。
「望月~望月だよなぁ」
私は不意に後ろから名前を呼ばれ、振り返った。
「やっぱり望月みちるだ。
すぐ判ったよ」
私を見つけて嬉しそうに笑っているその人は、中学時代の同級生だった。
「こ、紺野くん・・!?わぁ、久し振りね。
元気い?」
元気い?」
私は、この懐しい顔に思わず駆け寄った。
「何やってんだよ、買い物か~」
紺野くんは、私の抱えている包みを見て言った。
「うん、主人に頼まれちゃって・・」
私は懐かしさの反面、少し照れくさくもあり下を向いた。
「主人・・て、結婚したのか。
そうだよな、俺達もう二十八だもんな。
もうガキの一人や二人居てもおかしくないか」
紺野くんはそう言って、昔とちっとも変わらない顔で笑った。
「紺野くんは~」
「俺か~俺はまだまだ。
仕事が忙がしくってね」
「そう。
お仕事なにしてるの~」
「うーん、そうだな。
映像関係・・ってとこかな」
詳しく説明していたら、もっと時間がかかるのだろう。
彼は大まかな返答をした。
「ヘー、凄いじゃない」
私は口元で小さく拍手の真似事をした。
「それ程でも無いさ。
もうちょっと喋りたいんだけど、今日は生憎忙いでるんだ。
もし良かったら後日電話をくれないか。
飯でも食いながら昔話をしよう」
紺野くんはポケットから手帳とペンを取り出すと、走り書きしてメモを私の手に握らせた。
「俺の携帯の番号。
いつでもかけて来いよ、じやあな」
「・・うん、お仕事頑張って・・」
さよならの挨拶もままならぬまま、彼は走り出した。
「あっと、旦那に見つかるなよ」
紺野くんは一旦振り返ると、悪戯をしめし合わせた少年のような台詞を残し、再び背中を見せた。
「・・紺野くん・・」
私は、彼のくれたメモを胸に当て、深く息を吸った。
心臓の音が、耳のすぐ隣りで鳴っているような気がした。
紺野くんとは、中学時代の三年間同じクラスで過ごした。
明るく活発でウィットに富んでいた彼は、人気が有り女の子達に良くモテた。
あの時は気の無い振りをしていたけれど、今になって思えば中学時代を振り返ると必ず彼の顔が脳裏に浮かんでいた。
私はしばらくその場で、彼の電話番号を数回反復して読むと、バックの中にそっと仕舞い込んだ。
大切なメモの入ったバックを肩に抱え直すと、私は込み合った補道を巧みに歩いて行った。
すぐに電話をかけたら、ふしだらな女に思われてしまうだろうか・・。
数日の時の流れを、胸の底が焦げつきそうな思いで待ち、私は、はやる心を押えて彼のメモの番号をプッシュした。
数回のコールの後、細かいノイズと共に彼の声が聞こえた。
「もしもし・・」
「・・あ、紺野くん~みちるです」
かすかな緊張が私を取り巻く。
「ああ、望月か。
電話サンキュー。
旦那には見つかってないか~」
彼の屈詫の無い声が耳に心地良い。
「いやね、紺野くん。
主人の事は関係無いわ。
私達同級生じゃない」
「昔は同級生でも、今は人妻だからなぁ。
やっぱヤバイんじゃないの~」
携帯電話を握り締めて冗談めかす彼の姿が浮かぶ。
「そんな事無いわ。
紺野くんは幼馴じみで兄弟みたいなものだもの。
ヤバい事なんてある訳無いわ」
私は、わざと意地悪く彼をつっぱねた。
「それよりさ、会おうよ」
「いいわ、いつ~」
「今夜」
「今夜?」
「・・ダメかな」
「・・いいわ。
主人には何とか言い訳するから」
「悪いな。
なんか強引だな、俺」
「そんな事・・」
「じゃあ、六時に渋谷・・」
「判ったわー」
電話を終えると、私は急いで主人一人分の食事を作り、丹念に身支度を整えると約束の時間に間に合うよう出掛けた。
私の心にそこはかとないときめきを覚えた。
「望月、すまない、少し遅くなった・・」
時計の針が六時を少し回った頃、彼は息を弾ずませてやって来た。
「お仕事と、忙がしそうね」
「まあね、これでも一応チーフなんだ」
「チーフ~出世したのね」
「いや、まだまだこれからさ。
行こう、近くにうまいレストランが有るんだ」
私は彼の横を肩を並べて歩いた。
それは中学時代、幾度となく夢に描いた光景だった。
こうして紺野くんと連れ添って歩き、楽しいお喋りをしながら食事をする。
卒業して、いつしか薄れかけていた物語が、十数年の時を経てにわかに香り立ち色付き始めていた。
だけど彼は、もう十五才のやんちゃな少年ではなく、広い背中と凄としたまなざしを併せ持つ大人の男に変身していた。
フレンチレストランの、純白のクロスのかかったテーブルに向い合わせに座り、フレンチのコースを年代物のワインをチョイスする。
暗が彼を、一体どんな経緯でここまで成長させてきたのか。
私の知らない彼の時間が、わずかな嫉妬さえも覚えさせた。
「望月、ワインはいけるくち~」
「ええ、少しなら」
私は、ソムリエが注ぐ、淡いベルドット色をした液体を眺めながらうなづいた。
「十三年振りの再会を祝して・・」
「乾杯」
薄氷のようなグラスが、細く高い音を立てて触れ合った。
十三年の間止まっていた時計が、今、再び動き始めた。
「・・紺野くん、私、ちょっと飲みすぎたかしら・・」
食事を終え、店を出て歩き出した途端、一気にお酒が廻ったのか、私は足元がおぼつかなくなり、すっかり紺野くんにしなだれかかっていた。
久し振りにお酒を飲んだせいか、それとも緊張のせいか、アルコールの廻りは私の予想以上に早かった。
「大丈夫か、望月。
ちゃんと家に帰れるか~」
彼は私の腰に手を回し、フラ付く体を支えていてくれた。
「へ、平気よ。
なんとか帰れそう・・」
私は、目の前でぐるぐる回転する地面を、一歩一歩踏みしめながら辿った。
踏みしめているはずの地面が、気が付くといつの間にか自分の頭の上にあった。
どうしてこんな所に私は頭を付けているのかしら・・。
続きを読む